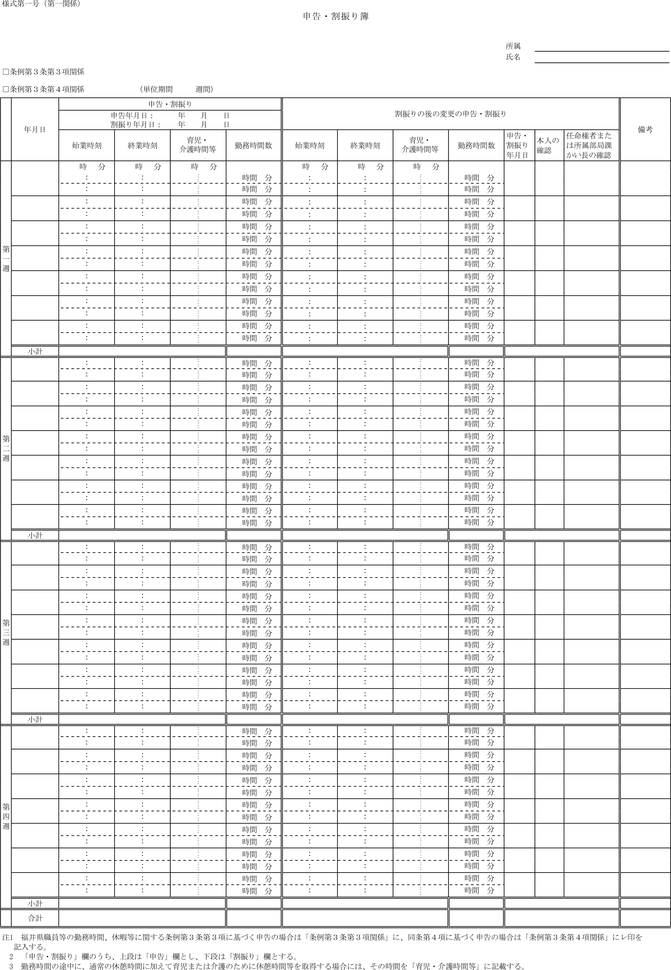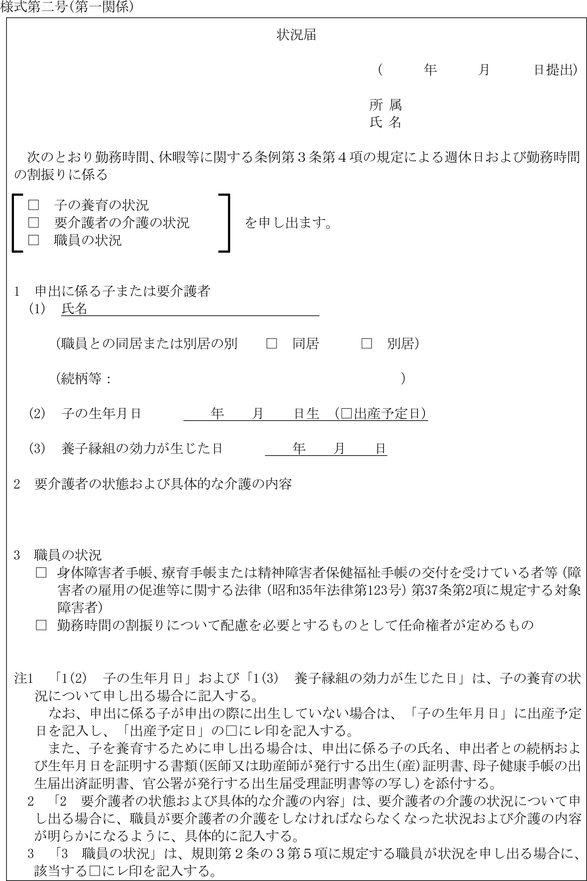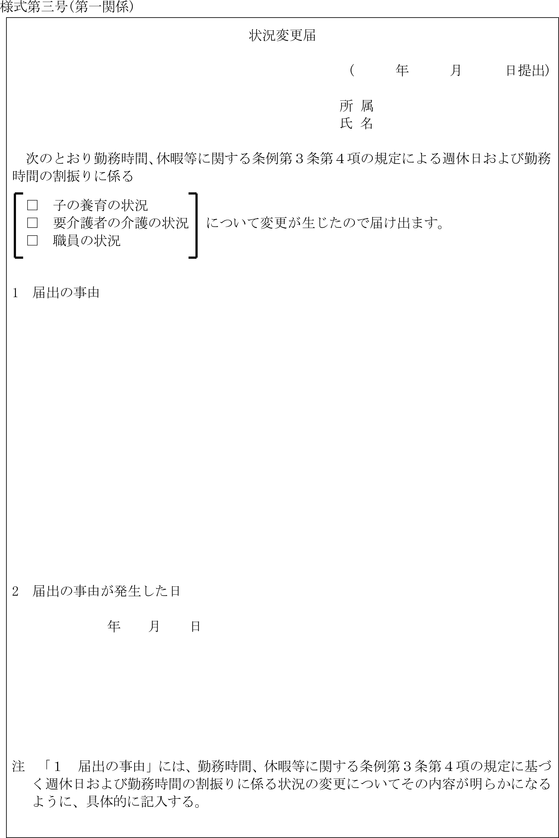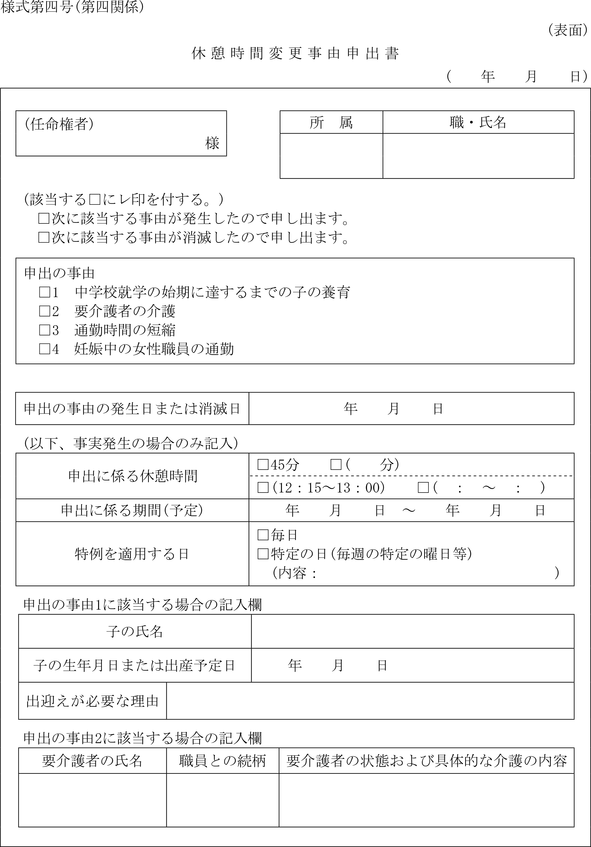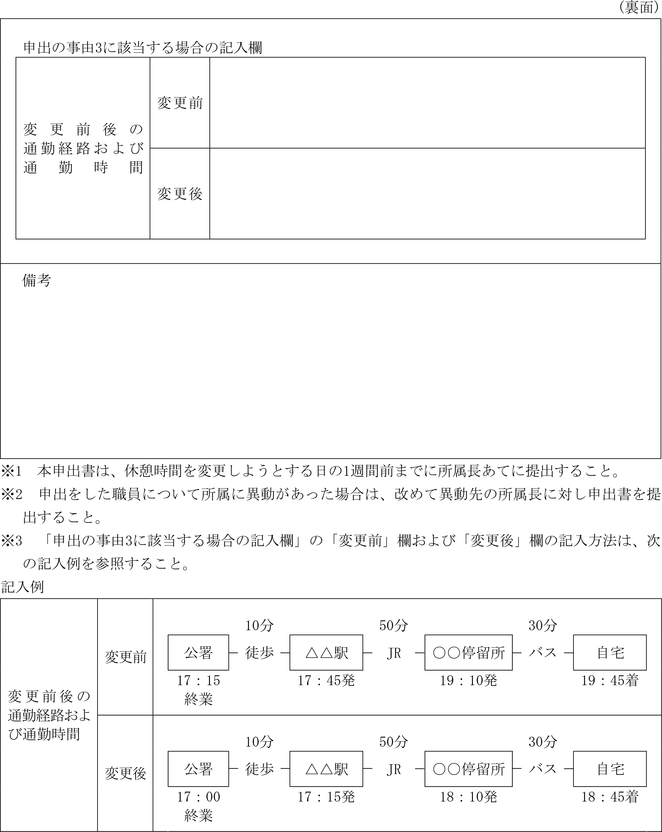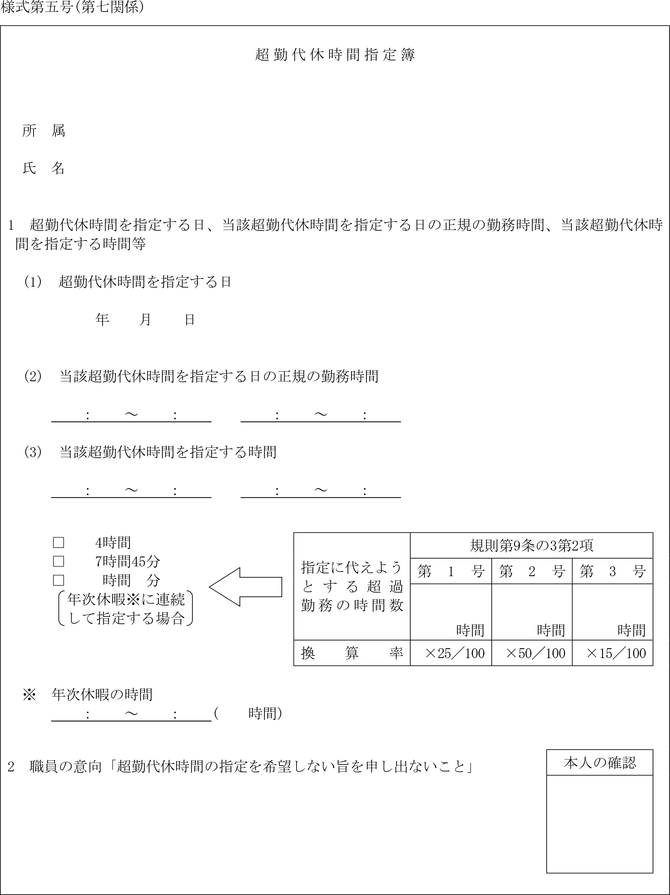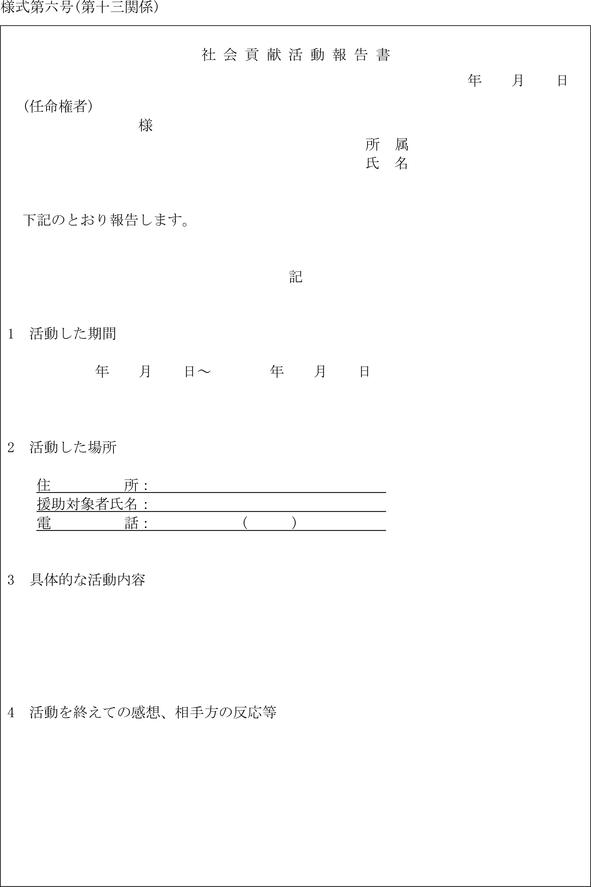○福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用方針
平成七年三月十六日福井県人事委員会告示第一号
福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用方針を次のように定める。
福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用方針
第一 一週間の勤務時間の特例の基準関係
1 任命権者は、
条例第二条第五項の規定により人事委員会の承認を得ようとするときは、次の事項を記載した文書により、事前に相当の期間を置いて行うものとする。
一 承認の対象となる職員の範囲
二 一週間当たりの勤務時間
三 当該勤務が必要かつやむを得ないものである理由
一 職員が日を単位として出張する日
二 職員が一日の執務の全部を離れて研修を受ける日
三 職員が休暇を使用して一日の勤務時間の全てを勤務しないことを予定していることが明らかな日
5
規則第二条の四第一項の規定による週休日の設定および勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するように行うものとする。この場合において、申告どおりに週休日を設け、または勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずる日について、それぞれ当該週休日を勤務日とするときまたは勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るときは、必要な限度において、当該支障が生ずる日以外の日について週休日とし、または勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るものとし、その週休日とする日または勤務時間数を変更する日の選択および勤務時間の割振りの変更に当たっては、できる限り、職員の希望を考慮するものとする。
一 申告された勤務時間を延長して勤務時間を割り振る日については、延長後の勤務時間が七時間四十五分を超えないようにし、申告された勤務時間を短縮して勤務時間を割り振る日については、短縮後の勤務時間が七時間四十五分を下回らないようにすること。
二 始業の時刻は、申告された始業の時刻または標準勤務時間(任命権者が、職員が勤務する部局または機関の職員の勤務時間帯等を考慮して、七時間四十五分となるように定める標準的な一日の勤務時間をいう。以下同じ。)の始まる時刻のうち早い時刻以後に設定し、かつ、終業の時刻は、申告された終業の時刻または標準勤務時間の終わる時刻のうち遅い時刻以前に設定すること。
6
規則第二条の四第二項第二号の場合における週休日および勤務時間の割振りの変更は、任命権者が当該週休日または当該勤務時間を変更しなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認める場合に限るものとし、かつ、前項第一号および第二号に掲げる基準に適合するように行うものとする。この場合において、当該週休日を勤務日とするときは、必要な限度において、その勤務日とする日以外の日を週休日とし、または当該勤務日とする日以外の日について既に割り振られている勤務時間数を変更することができ、変更日について既に割り振られている勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るときは、必要な限度において、当該変更日以外の日について既に割り振られている勤務時間数を変更して勤務時間を割り振ることができるものとし、その週休日とする日または既に割り振られている勤務時間数を変更する日の選択および勤務時間の割振りの変更に当たっては、できる限り、職員の希望を考慮するものとする。
一 父母の配偶者
二 配偶者の父母の配偶者
三 子の配偶者
四 配偶者の子
二
規則第二条の三第一項の規定により週休日を設け、および勤務時間を割り振った場合には、当該週休日および各勤務日の正規の勤務時間
三
規則第二条の四第一項の規定により週休日を設け、または勤務時間を割り振った場合には、当該週休日および各勤務日の正規の勤務時間
四
規則第二条の四第二項の規定により週休日および勤務時間の割振りを変更した場合には、変更により週休日となった日および変更された勤務日の正規の勤務時間
一部改正〔平成一三年人委告示一号・一七年三号・二〇年一号・令和五年二号〕
第二 週休日および勤務時間の割振りの特例の基準関係
1 任命権者は、
条例第四条第一項の規定により週休日および勤務時間の割振りを定める場合には、割振り単位期間(
規則第三条に規定する三週間または四週間ごとの期間をいう。)ができる限り多く連続するように一括して行うものとする。
2
条例第四条第二項ただし書の規定による人事委員会との協議(市町教育委員会にあっては、福井県教育委員会が行う。)は、次の事項を記載した文書により、事前に相当の期間を置いて行うものとする。
一 協議の対象となる職員の範囲
三 週休日および勤務時間の割振りの基準の内容
3 任命権者は、
条例第四条第二項ただし書の規定により人事委員会と協議した週休日および勤務時間の割振りについての定めを変更する場合には、変更の内容および理由を記載した文書により、人事委員会と協議するものとする。
4 任命権者は、
条例第四条第二項ただし書の規定により人事委員会と協議した週休日および勤務時間の割振りについての定めによる必要がなくなった場合には、速やかにその旨を人事委員会に報告するものとする。
一部改正〔平成一八年人委告示一号〕
第三 週休日の振替等関係
1 一の週休日について、週休日の振替(
条例第五条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を
条例第五条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)および四時間の勤務時間の割振り変更(
条例第五条の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を
同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)の双方を行うことができる場合には、できる限り、週休日の振替を行うものとする。
2 週休日の振替を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、週休日に変更される勤務日の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。
3 四時間の勤務時間の割振り変更を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、当該四時間の勤務時間の割振り変更が行われる職員の通常の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯の範囲内に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。
4
条例第三条第一項または
第四条の規定に基づき毎日曜日が週休日と定められている職員にあっては、祝日法による休日および年末年始の休日に割り振られている勤務時間については、できる限り、週休日の振替および四時間の勤務時間の割振り変更は行わないものとする。
5
規則第四条第五項の「連続する勤務時間」には、休憩時間をはさんで連続する勤務時間が含まれる。
一部改正〔平成二二年人委告示一号・二五年一号〕
第四 休憩時間関係
2
規則第四条の二第一号の「中学校就学の始期に達するまでの子」とは、満十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子をいい、
同号の「養育する場合」には当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合が含まれるものとする。
3
規則第四条の二第三号の「人事委員会が別に定める時間」は、交通機関を利用するために待つ時間および乗り継ぎのために待つ時間とする。
4
規則第四条の二第四号について、「交通機関の混雑の程度」とは、職員が通常の勤務をする場合の退庁の時間帯における常例として利用する交通機関の混雑の程度をいい、母体または胎児の健康保持への影響については、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導または同法第十三条に規定する健康診査における指導事項(以下「保健指導等における指導事項」という。)により判断するものとする。
5
規則第四条の二の申出は、休憩時間変更事由申出書(
様式第四号)により行うものとする。ただし、これによりがたい場合は、任命権者において所要の調整を行うことができる。
6 任命権者は、
規則第四条の二の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認することができる。
全部改正〔平成一一年人委告示一号〕、一部改正〔平成一九年人委告示一号・令和五年二号〕
第五 休息時間関係
1 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。
2
規則第五条第一号の「おおむね四時間」は、三時間三十分から四時間三十分までの間の時間とする。
3
規則第五条第一号の「人事委員会が定める回数」は、一回の勤務に割り振られた勤務時間が十時間十五分未満である場合にあっては一回、当該勤務時間が十時間十五分以上十六時間以下である場合にあっては二回とする。
4 四時間の勤務時間の割振り変更を行った場合において、勤務時間を割り振ることをやめることとなった日および新たに勤務することを命ずることとなった日については、当該四時間の勤務時間の割振り変更後におけるそれぞれの日の勤務時間の割振りに応じた休息時間を置くものとする。
全部改正〔平成二二年人委告示一号〕
第六 宿日直勤務関係
1
条例第八条第一項の規定による人事委員会への許可の申請は、次の事項を記載した文書により行うものとする。
一 勤務の内容
二 勤務の時間および仮眠の時間
三 勤務に従事する職員の範囲
四 一回当たりの勤務人数
五 一月当たりの勤務回数
六 職員への周知方法
七 勤務者の休憩・仮眠施設の概要
2 任命権者は、
条例第八条第一項の規定により人事委員会の許可を得た勤務の必要がなくなった場合には、速やかにその旨を人事委員会に報告するものとする。
一部改正〔平成一七年人委告示七号〕
第七 超勤代休時間の指定関係
2
規則第九条の三第五項に規定する超勤代休時間の指定を希望しない旨の申出は、超勤代休時間の指定前に行うものとする。
3
条例第八条の二第一項の規定に基づく超勤代休時間の指定は、超勤代休時間指定簿により、その指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る六十時間超過月の末日の直後の給料の支給日までに行うものとする。
4 超勤代休時間指定簿は
様式第五号によるものとする。ただし、これによりがたい場合は、任命権者において所要の調整を行うことができる。
5 超勤代休時間指定簿は、一の超勤代休時間ごとに一部作成するものとする。ただし、必要に応じて、複数の超勤代休時間について同一の超勤代休時間指定簿によることができる。
追加〔平成二二年人委告示一号〕、一部改正〔令和五年人委告示二号〕
第八 育児または介護を行う職員の深夜勤務の制限関係
1
条例第八条の三第一項の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までをいう。
2 任命権者は、
条例第八条の三第一項の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る期間における職員の業務内容、業務量、代行者の配置の難易等を総合的に検討して行うものとする。
4
規則第九条の五第二項の規定による通知は、書面により行うものとし、公務の運営に支障がある場合には、併せて当該支障のある日、時間および理由を通知するものとする。
6
規則第九条の七において準用する
規則第九条の六第一項第二号の「要介護者と当該深夜勤務制限請求をした職員との親族関係が消滅したとき」とは、深夜勤務制限請求に係る要介護者が、離婚、婚姻の取消し、離縁等により職員の親族でなくなった場合をいう。
追加〔平成一一年人委告示一号〕、一部改正〔平成一三年人委告示一号・一四年三号・二二年一号〕
第九 育児または介護を行う職員の超過勤務の制限関係
2
条例第八条の三第二項および
第三項の「業務を処理するための措置」とは、業務の処理方法、業務分担または人員配置を変更する等の措置をいう。
3
条例第八条の三第二項の「災害その他避けることのできない事由」とは、地震による災害等通常予見し得る事由の範囲を超え、客観的に避けられないことが明らかなものをいう。
4
条例第八条の三第三項の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までをいう。
5 任命権者は、
条例第八条の三第三項の規定による超過勤務の制限が、育児または介護を行う職員が働きながら子の養育または要介護者の介護を行うための時間を確保することができるようにするものであることを考慮し、
同項の規定により超過勤務が制限される職員に、恒常的に超過勤務をさせること、特定の期間に過度に集中して超過勤務をさせることその他の当該時間の確保を妨げるような超過勤務をさせることがないように留意しなければならない。
7
規則第九条の九第四項の規定による通知は、変更した超過勤務制限開始予定日を記載した書面により行うものとする。
8
規則第九条の十第一項第三号の「同居しないこと」とは、超過勤務を制限することとなる期間を通して同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。
9
規則第九条の十一において準用する
規則第九条の十第一項第二号の「要介護者と当該超過勤務制限請求をした職員との親族関係が消滅したとき」とは、超過勤務制限請求に係る要介護者が、離婚、婚姻の取消し、離縁等により職員の親族でなくなった場合をいう。
追加〔平成一四年人委告示三号〕、一部改正〔平成二二年人委告示一号・二号〕
第十 休日の代休日の指定関係
1
条例第十条第一項の規定に基づく代休日の指定は、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。
2
規則第十条第三項に規定する代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行うものとする。
一部改正〔平成一一年人委告示一号・一四年三号・二二年一号〕
第十一 年次休暇関係
2
条例第十二条第一項第二号の新たに職員となる者には、非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)から引き続き常勤職員となった者を含む。
3
規則第十二条の二第一項第一号の新たに職員となる者には、退職後引き続き地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項もしくは第二項の規定により採用された者を含まないものとする。
6
規則第十二条の二第一項第二号の「使用した年次休暇に相当する休暇の日数」および
同条第四項第一号ロの「使用した年次休暇または年次休暇に相当する休暇の日数」に一日未満の端数があるときは当該日数を切り上げた日数とし、
同号イの「年次休暇または年次休暇に相当する休暇の残日数」に一日未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた日数とする。
7
規則第十二条の二第一項第二号の「人事委員会が別に定める日数」は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。ただし、その日数が企業職員等から引き続き新たに定年前再任用短時間勤務職員等となった日において
規則第十二条の二第一項第一号の規定を適用した場合に得られる日数(以下「新たに定年前再任用短時間勤務職員等となった日からの基本日数」という。)に満たない場合にあっては、新たに定年前再任用短時間勤務職員等となった日からの基本日数とする。
一 当該年において、定年前再任用短時間勤務職員に相当する企業職員等となった者であって、引き続き定年前再任用短時間勤務職員となったもの (次号に掲げる職員を除く。) 当該企業職員等から引き続き定年前再任用短時間勤務職員等となった日において
条例第十二条第一項第二号の規定を適用した場合に得られる日数に、企業職員等となった日において新たに企業職員等であったときと一週間当たりの勤務日および勤務時間が同一の定年前再任用短時間勤務職員等(以下「みなし定年前再任用短時間勤務職員等」という。)として在職したものとみなして
同号の規定を適用した場合に得られる日数(第九項第二号ロにおいて「定年前再任用短時間勤務職員等みなし付与日数」という。)から、新たに定年前再任用短時間勤務職員等となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た数を加えて得た日数
二 当該年において、新たに定年前再任用短時間勤務職員等となった者(企業職員等から引き続き定年前再任用短時間勤務職員等となった者を除く。)であって、引き続き定年前再任用短時間勤務職員等に相当する企業職員等となり、当該企業職員等から引き続き定年前再任用短時間勤務職員等となったもの 前号に定める日数に、当該企業職員等となった日の前日における年次休暇の残日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を加えて得た日数
8
規則第十二条の二第二項の人事委員会が認めるものは、特別の法律の規定により、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二の規定の適用について、同条第一項に規定する公庫等職員とみなされる者を使用する法人とする。
9
規則第十二条の二第四項の「人事委員会が別に定める日数」は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。ただし、その日数が新たに定年前再任用短時間勤務職員等となった日からの基本日数に満たない場合にあっては、新たに定年前再任用短時間勤務職員等となった日からの基本日数とする。
一 当該年の前年に定年前再任用短時間勤務職員等に相当する企業職員等であった者であって、引き続き当該年に定年前再任用短時間勤務職員等となったもの 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
イ 当該年の初日に定年前再任用短時間勤務職員等となった場合 定年前再任用短時間勤務職員等となった日において新たに定年前再任用短時間勤務職員等となったものとして
条例第十二条第一項第一号または
第二号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該年の前年における年次休暇に相当する休暇の残日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とし、当該日数が当該年の前年における当該企業職員等として在職した期間をみなし定年前再任用短時間勤務職員等として在職したものとみなして
同項第一号または
第二号の規定を適用した場合に得られる日数を超えるときは、当該日数。ロにおいて同じ。)を加えて得た日数
ロ 当該年の初日後に定年前再任用短時間勤務職員等となった場合 新たに定年前再任用短時間勤務職員等となった日からの基本日数に、当該年の初日においてみなし定年前再任用短時間勤務職員等となったものとみなして当該年における定年前再任用短時間勤務職員等に相当する企業職員等として在職した期間を在職期間とみなして
条例第十二条第一項第二号の規定を適用した場合に得られる日数(次号において「初日みなし付与日数」という。)と当該年の前年における年次休暇に相当する休暇の残日数とを合計した日数から、同日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数を加えて得た日数
二 当該年の前年に定年前再任用短時間勤務職員等であった者であって、引き続き当該年に定年前再任用短時間勤務職員等に相当する企業職員等となり、当該企業職員等から引き続き再び定年前再任用短時間勤務職員等となったもの 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
イ 当該年の初日に定年前再任用短時間勤務職員等に相当する企業職員等となった場合 企業職員等から引き続き再び定年前再任用短時間勤務職員等となった日において
規則第十二条の二第一項第一号の規定を適用した場合に得られる日数(以下この号において「再び定年前再任用短時間勤務職員等となった日からの基本日数」という。)に、初日みなし付与日数と当該年の前年における年次休暇の残日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数。以下この号において同じ。)とを合計した日数から、同日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数を加えて得た日数
ロ 当該年の初日後に定年前再任用短時間勤務職員等に相当する企業職員等となり、当該企業職員等から引き続き定年前再任用短時間勤務職員等となった場合 再び定年前再任用短時間勤務職員等となった日からの基本日数に、初日みなし付与日数、定年前再任用短時間勤務職員等みなし付与日数および当該年の前年における年次休暇の残日数を加えて得た日数から、当該年において同日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数および使用した年次休暇の日数(これらの日数に一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数
10 定年前再任用短時間勤務職員等であって、当該年に勤務日等が変更され、変更後の勤務日等が変更前のそれを上回ることとなった場合における年次休暇の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 当該年において新たに定年前再任用短時間勤務職員等となった者 新たに定年前再任用短時間勤務職員等となった日から勤務日等の変更があった日の前日までの期間を
規則第十二条の二第一項第一号の在職期間とみなして
同号の規定を適用した場合に得られる日数に、勤務日等の変更があった日において新たに定年前再任用短時間勤務職員等となったものとみなして
同号の規定を適用した場合に得られる日数を加えて得た日数から、勤務日等の変更があった日の前日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数
二 当該年の前年から定年前再任用短時間勤務職員等である者 当該年の一月一日から勤務日等の変更があった日の前日までの期間を
規則第十二条の二第一項第一号の在職期間とみなして
同号の規定を適用した場合に得られる日数に、勤務日等の変更があった日において新たに定年前再任用短時間勤務職員等となったものとみなして
同号の規定を適用した場合に得られる日数および当該年の前年における年次休暇の残日数(当該日数に一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を加えて得た日数から、当該年において勤務日等の変更があった日の前日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数
11
規則第十二条の二第五項の「使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないもの」とは、
条例第十二条第一項第三号に規定する企業職員等として在職した期間において使用した年次休暇に相当する休暇の日数または当該年の前年の末日における年次休暇に相当する休暇の残日数が把握できない者をいい、その者の年次休暇の日数は、当該使用した年次休暇に相当する休暇の日数を把握できない期間において当該期間に応じて
規則別表第一の日数欄に掲げる日数の年次休暇に相当する休暇を使用したものとみなし、または当該把握できない残日数を二十日とみなして、それぞれ
規則第十二条の二第一項第二号または
同条第四項の規定を適用した場合に得られる日数とする。
12
規則第十二条の三の「当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数」に一日未満の端数がある場合には、
同条の「当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数」は、当該端数を切り上げた日数を減じて得た日数に、当該変更の日の前日において
規則第十四条第四項の規定に基づき得られる時間数から当該端数の時間数を減じて得た時間数を当該得られる時間数で除して得た数に相当する日数を加えて得た日数とする。
13
規則第十三条の「使用した日数」に一日未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた日数とする。
14 繰り越された年次休暇の有効期間は、一年間である。
15 繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
16 一日を単位とする年次休暇は、育児短時間勤務職員等および定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員ならびに不斉一型短時間勤務職員にあっては一回の勤務に割り振られた勤務時間が七時間を超え七時間四十五分を超えない時間とされている場合において当該勤務時間の全てを勤務しないときに、斉一型短時間勤務職員にあっては一日の勤務時間の全てを勤務しないときに使用できるものとする。
17 半日を単位とする年次休暇は、次のいずれにも該当する場合であって、任命権者が別に定めるときに使用できるものとする。
一 一回の勤務に割り振られた勤務時間が七時間四十五分を超えない時間とされている場合
二 休憩時間(任命権者が休憩時間を一回の勤務について二回以上に分割して職員に与える場合にあっては、それぞれの休憩時間のうち最も長い休憩時間)の前後のいずれか一方の勤務時間の全てを勤務しない場合
18 年次休暇を請求した後に、当該年次休暇の日について週休日の振替等または代休日の指定が行われた場合には、週休日に変更された日、勤務日の勤務時間のうち週休日に割り振られた四時間または代休日に指定された日については、年次休暇として取り扱わないものとする。
一部改正〔平成一一年人委告示一号・一三年一号・一四年三号・四号・一七年三号・一九年一号・二〇年一号・二二年一号・三号・令和五年三号〕
第十二 病気休暇関係
1
条例第十三条第一項の「疾病」には予防接種による著しい発熱等が含まれ、
同項の「療養する」場合には負傷または疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。
2
規則第十六条第一項の「一年以内」、「百八十日以内」および「九十日以内」とは、それぞれ引き続いた期間をいうものとし、その引き続いた休暇日数の計算については、次の取扱いによるものとする。
一 正規の勤務時間の途中において勤務しないことの原因が発生し、勤務を休み始めたときは、その日を含めて計算する。
二 当該日数には、週休日、休日および代休日を含めて計算する。
三 病気休暇の承認を与えた期間内にたとえ出勤したことがあっても、その期間は中断されないものとする。ただし、勤務できることが医師の診断書に基づいており、かつ、勤務することを任命権者が認めた場合は、この限りでない。
四 病気休暇の期間中に
条例第十四条に規定する特別休暇に相当する日があり、特別休暇が任命権者により承認された場合においても、当該病気休暇は、中断または延長されないものとする。
一 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の規定により厚生労働大臣が指定する指定難病
二 福井県特定疾患治療研究事業実施要綱第三に掲げる対象疾患
三 保健指導等における指導事項として休業の措置を要する旨の指導が行われた症状またはこれに相当すると任命権者が認める症状の疾病
5
規則第十六条第二項の医師の診断書は、女性職員が前項第三号に掲げる疾病により療養を要する場合において、妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成九年労働省告示第百五号)3(1)に定める母性健康管理指導事項連絡カード(以下「指導事項連絡カード」という。)をもってこれに代えることができるものとする。この場合においては、任命権者は、できる限り当該病気休暇を承認するものとする。
一部改正〔平成一〇年人委告示一号・一一年一号・一三年一号・一四年三号・一九年一号・二二年一号・二号・二七年二号・令和五年一号〕
第十三 特別休暇関係
1
規則第十七条第一項第一号の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法についての同意を求める住民投票、憲法改正の場合の国民投票、地方公共団体の議会の議員または長の解職の請求があった場合の投票等公民に認められる国家または公共団体の公務に参加する権利をいう。
3
規則別表第三の五の項、十の項、十八の項から二十の項までおよび二十三の項の「出産予定日証明書等」とは、医師または助産師による診断書または証明書、指導事項連絡カードその他妊娠の週数または出産予定日を確認できるものをいい、職員が希望する場合には、母子保健法第十六条第一項の母子健康手帳(以下「母子健康手帳」という。)をもってこれに代えることができるものとする。
一 職員は、一日における二回分の休暇を連続して請求し、または承認を受けることができる。
二
規則別表第三の六の項に掲げる場合における休暇に係る期間は、男性職員にあっては、当該男性職員以外のその子の親が、同日においてこの号に掲げる場合における休暇を請求し、もしくはこれに相当する休暇の承認を受け、または労働基準法第六十七条第一項の規定により同日において育児時間を請求した場合には、一日二回それぞれ三十分から当該請求または承認に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない範囲内における期間とする。
一 「配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末血幹細胞移植のため末血幹細胞を提供する場合」には、骨髄または末血幹細胞の提供希望者の登録を実施する者(以下「骨髄バンク」という。)を介さないで提供する場合を含むものとする。
二
規則別表第三の八の項の「医師の診断書等」とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類とする。
イ 骨髄バンクに対して登録の申出を行うことに伴い検査が必要な場合 骨髄バンクが発行する検査を依頼する通知
ロ 骨髄バンクを介して骨髄または末血幹細胞を提供することに伴い、検査、入院等が必要な場合 骨髄バンクが発行する証明書または医師の診断書
ハ 骨髄バンクを介さずに骨髄または末血幹細胞を提供することに伴い、検査、入院等が必要な場合 医師の診断書
6
規則別表第三の九の項の「七日以内」は、結婚の日(社会通念上、結婚と認められる日をいう。)の五日前の日から当該結婚の日後一年を経過する日までの期間において、一暦日ごとに分割することができる。ただし、任命権者において特に必要と認めるときは、この限りでない。
一 「入院の付添い等」とは、出産に係る入院または退院の際の付添い、出産時の付添い、出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等をいう。
二
規則別表第三の十の項の「二日以内」は、一日または一時間ごとに分割することができる。
9
規則別表第三の十一の項の「一の年」とは一暦年をいい、同項の「五日(当該親族等が二人以上の場合にあっては、十日)以内」は一日または一時間ごとに分割することができる。
10
規則第十七条第一項第十二号の休暇の期間は、葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては往復に要する日数を加えた日数とし、任命権者が職員の申請に基づき
規則別表第三の十二の項に掲げる期間の範囲で承認を与えた期間の最初の日から起算する。
一
規則別表第三の十四の項の「一の年」とは一暦年をいい、同号の「原則として連続する五日以内」は、特に必要があると認められる場合には、一日または四時間(勤務時間の始めまたは終わりにおけるそれぞれ連続する(休憩時間を除く。)四時間とする。育児短時間勤務職員等および定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、七時間四十五分以外の勤務時間が割り振られている日を除く。)ごとに分割することができる。
二 任命権者は、休暇の計画的な使用を図るとともに、あらかじめ各職員の休暇取得時期を把握するため計画表を作成するものとする。
12
規則第十七条第一項第十五号の「これらに準ずる場合」とは、例えば、地震、水害、火災その他の災害により単身赴任手当の支給に係る配偶者等の現住居が滅失し、または損壊した場合で、当該単身赴任手当の支給を受けている職員がその復旧作業等を行うときをいう。
一 保健指導には、市町村、医師、歯科医師、助産師または保健師が行う保健指導または歯科保健指導で母親学級、両親学級等の集団で行われるものを含むものとする。
二 一の健康診査の結果に基づいて別の日に保健指導が実施される場合には、これらをあわせて
規則別表第三の十八の項に掲げる場合における休暇一回とみなす。
一 「交通機関等の混雑の程度」とは、当該女性職員が通常の勤務をする場合の登庁または退庁の時間帯における次の混雑の程度とする。
イ 当該職員が常例として利用する交通機関の混雑の程度
ロ 当該職員が常例として利用する自家用車の経路における道路の混雑の程度で、保健指導等における指導事項として通勤緩和の措置を要する旨の指導が行われたものまたはこれに相当すると任命権者が認めたもの
二 前号イの場合において、保健指導等における指導事項がなく、かつ、母体または胎児の健康保持に影響がある程度の判断が困難なときは、任命権者は、医師の診断書の提出を求め、これにより判断するものとする。
三
規則別表第三の十九の項の「一日一時間以内」とは、正規の勤務時間の始めまたは終わりにつき、一日を通じて一時間を超えない範囲内で、おのおの必要とされる時間をいうものとする。
四
規則別表第三の十九の項の「その旨を証明する書類」とは、指導事項連絡カードまたは医師の診断書をいい、職員が希望する場合には、母子健康手帳をもってこれに代えることができるものとする。
五 職員から休暇の請求があった場合には、任命権者は、特別休暇・病気休暇・介護休暇簿に所要の事項を記入するとともに、出勤簿に妊娠通勤緩和のための特別休暇である旨を表示し、勤務時間の管理を適正に行わなければならない。
一 「つわり等」とは、つわり、妊娠阻、妊娠中毒症、切迫流産などをいう。
二 著しく困難な場合の認定は、所属長において行い、職員から当該特別休暇の請求があった場合には、原則として特別の証明書類がないときも認定するものとする。
一 「報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合」とは、交通費等の実費弁償以外にその活動の対価としての金品を得ないで、かつ、ボランティア切符、ボランティア貯蓄その他将来的な見返りを期待させるものによらずに当該活動を行う場合をいう。
二 被災地またはその周辺の地域は相当規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)またはその属する都道府県もしくはこれに隣接する都道府県として、「相当規模の災害」とは災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項各号に掲げる程度の規模の災害を、「その他の被災者を支援する活動」とは居宅の損壊または水道、電気もしくはガスの遮断等により日常生活を営むことに支障がある者に対して行う炊き出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。
三 「人事委員会が定めるもの」とは、次に掲げる施設とする。
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設およびそれ以外の同条第一項に規定する障害福祉サービスを行う施設(ハおよびトに掲げる施設を除く。)、同条第二十七項に規定する地域活動支援センターならびに同条第二十八項に規定する福祉ホーム
ロ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設および視聴覚障害者情報提供施設
ハ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の障害児入所施設、児童発達支援センターおよび児童心理治療施設ならびに児童発達支援センター以外の同法第六条の二の二第二項および第三項に規定する施設
ニ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホームおよび特別養護老人ホーム
ホ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項の保護施設のうち救護施設、更生施設および医療保護施設
ヘ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設および同条第二十九項に規定する介護医療院
ト 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項の病院
チ 学校教育法第一条に規定する特別支援学校
リ イからチまでに掲げる施設のほかこれらに準ずる施設として事務局長が定めるもの
四 「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯および補修、雪下ろし、慰問その他直接的な援助をいう。
五
規則第十七条第一項第二十一号ハに掲げる活動のうち、主として、活動の仲介を行っている団体および自らも主体となって活動を行う団体を通さない活動について休暇の承認を受けた職員は、事後において速やかに、社会貢献活動報告書(
様式第六号)により任命権者に報告を行うものとする。
六
規則別表第三の二十一の項の「一の年」とは、一暦年をいい、同項の「五日以内」は一暦日ごとに分割することができる。
七
規則別表第三の二十一の項の「社会貢献活動計画書」については、活動の仲介を行っている団体および自らも主体となって活動を行う団体等の募集要項等により、職員が社会貢献活動計画書に記載すべき事項について任命権者が把握している場合には、任命権者は職員にその提出を免除することができる。
一
規則別表第三の二十二の項の「勤続期間が三十年に達し、永年勤続職員表彰を受けた職員」および「勤続期間が二十年に達し、永年勤続職員表彰を受けた職員」の「勤続期間」の計算については、任命権者の定める基準によるものとする。
ハ 福井県警察の表彰に関する訓令(平成九年福井県警察本部長訓令第二号)第四条第二号に該当する者が受ける表彰
三
規則別表第三第二十二号の「勤続期間が十年に達した職員」とは、職員として採用された日の翌日から起算して、在職した期間が十年に達した職員をいう。
四
規則別表第三第二十二号の「人事委員会が定める期間」とは、勤続期間が三十年に達し、永年勤続職員表彰を受けた職員および勤続期間が二十年に達し、永年勤続職員表彰を受けた職員にあっては休暇を受ける事由に該当した日の翌日から、勤続期間が十年に達した職員にあっては休暇を受ける事由に該当した日以後における最初の四月一日から起算して一年(次に掲げる期間を除く。)を経過する日までとする。
イ 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七第一項の派遣の期間
ロ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定による派遣の期間
ニ 国または他の地方公共団体において人事交流等により採用され、在職した期間
ホ 国もしくは他の地方公共団体またはその他の団体において任命権者の命令を受けて研修等に従事した期間
一 「当該出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する」とは、職員の妻の出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらを監護することをいう。
一 「人事委員会が定める世話」とは、次に掲げる世話とする。
イ 要介護者の介護
ロ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
二
規則別表第三の二十四の項の「一の年」とは一暦年をいい、同項の「五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)以内」は一日または一時間ごとに分割することができる。
一 「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいう。
二
規則別表第三の二十六の項の「一の年」とは一暦年をいい、同項の「六日(当該通院等が体外受精または顕微授精に係るものである場合にあっては、十日)以内」は一日または一時間ごとに分割することができる。
三 当該特別休暇を受けようとする場合には、原則として医師の診断書等の提出は不要とする。ただし、任命権者は、必要に応じて医師の診断書等の提出を求めることができる。
21
規則第十七条第二項に規定する期間の計算については、四時間または一時間を単位とする場合を除くほか、正規の勤務時間の途中において勤務しないことの原因が発生し、特別休暇を取得し始めたときは、その日から起算するものとし、その期間中には週休日、休日および代休日を含むものとする。
22
規則第十七条第二項ただし書の「人事委員会が別に定める期間」は、育児短時間勤務職員等および定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員と同様とする。ただし、
規則第十七条第一項第九号、
第十四号、
第二十号および
第二十一号に掲げる場合における特別休暇の期間については、次の各号に掲げる育児短時間勤務職員等および定年前再任用短時間勤務職員等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日数以内とする。
一
規則第十二条第一号に掲げる斉一型短時間勤務職員(以下「斉一型短時間勤務職員」という。)
規則別表第三の中欄に掲げる日数に一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数(当該日数に一日未満の端数がある場合にあっては、当該日数が一日に満たないときはこれを一日とし、当該日数が一日を超えるときはこれを四捨五入して得た日数とする。)
二
規則第十二条第二号に掲げる不斉一型短時間勤務職員(以下「不斉一型短時間勤務職員」という。)
規則別表第三の中欄に掲げる日数に七・七五を乗じて得た時間数に
条例第二条第二項もしくは育児休業法第十七条の規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等の勤務時間、
条例第二条第三項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間または
同条第四項の規定に基づき定められた任期付短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、七時間四十五分を一日として日に換算して得た日数(当該日数に一日未満の端数がある場合にあっては、当該日数が一日に満たないときはこれを一日とし、当該日数が一日を超えるときはこれを四捨五入して得た日数とする。)
23
規則第十七条第一項第十号の休暇について
規則別表第三の中欄に規定する期間、
同項第十一号、
第二十四号もしくは
第二十六号の休暇について同表の中欄に規定する一の年の初日から末日までの期間または
同項第二十三号に規定する出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日後八週間を経過する日までの期間(以下この項において「対象期間」という。)内において、
規則第十二条の三各号に掲げる場合または勤務時間の変更等に該当したときは、当該該当した日(その日が対象期間の初日である場合を除く。以下この項において「該当日」という。)における
規則第十七条第一項第十号、
第十一号、
第二十三号、
第二十四号または
第二十六号の休暇(以下この項において「特定休暇」という。)の日数および時間数は、次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数および時間数とする。この場合において、対象期間内に二以上の該当日があるときは、直前の該当日を対象期間の初日と、当該直前の該当日においてこの項の規定を適用した場合に得られる日数および時間数を当該該当日における特定休暇の日数および時間数とそれぞれみなして、各々の該当日について
同項の規定を順次適用した場合に得られる日数および時間数とする。
一 対象期間の初日から該当日の前日までの間に使用した特定休暇の日数に一日未満の端数がない場合 対象期間の初日における特定休暇の日数から、同日から該当日の前日までの間に使用した当該特定休暇の日数を減じて得た日数
二 対象期間の初日から該当日の前日までの間に使用した特定休暇の日数に一日未満の端数がある場合 対象期間の初日における特定休暇の日数から、同日から該当日の前日までの間に使用した当該特定休暇の日数(当該端数を切り上げた日数)を減じて得た日数および該当日において次項の規定により得られる時間数から当該端数の時間数を減じて得た時間数(当該時間数が零を下回る場合にあっては、零)
24 四時間または一時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって一日とする。
一 次号および第三号に掲げる職員以外の職員 七時間四十五分
二 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(七時間四十五分を超える場合にあっては七時間四十五分とし、一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)
三 不斉一型短時間勤務職員 七時間四十五分
25 不斉一型短時間勤務職員が一日に割り振られた勤務時間のすべてまたは一日当たりの勤務時間(当該時間に一時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)以上の時間について特別休暇を取得した場合には、一日を取得したものとする。
一部改正〔平成九年人委告示一号・一〇年一号・一一年一号・一二年一号・二号・一三年一号・一四年一号・三号・四号・一五年一号・一六年一号・一七年三号・七号・一八年四号・一九年一号・二号・二〇年一号・二号・二一年一号・三号・二二年一号・二号・二三年一号・三号・二四年一号・二号・三号・二五年一号・二六年一号・二七年一号・二九年一号・三〇年一号・令和三年一号・五年一号・二号・三号・五号・六年一号〕
第十四 介護休暇関係
2 職員の介護休暇を承認した任命権者と当該職員が所属する給料の支給義務者が異なる場合においては、当該任命権者は、当該支給義務者に介護休暇を承認した旨を通知しなければならない。介護休暇の承認を取り消した場合等においても、同様とする。
3
規則第十八条第三項の規定による指定期間の延長の指定の申出は、できる限り、指定期間の末日から起算して一週間前の日までに行うものとし、
同項の規定による指定期間の短縮の指定の申出は、できる限り、当該申出に係る末日から起算して一週間前の日までに行うものとする。
4 任命権者は、
規則第十八条第五項の規定により指定期間を指定する場合において、
規則第十八条第九項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日として申出の期間または延長申出の期間から除く日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。
5
規則第十八条第八項の「人事委員会が定める場合」は、次に掲げる場合とし、
同項の「人事委員会が定める期間」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
一 一回の指定期間の初日から末日までの期間が二週間未満である場合、当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間
二 一回の指定期間の初日から末日までの期間が二週間以上である場合であって、初日請求日から二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合、初日請求日から当該末日までの期間
三 一回の指定期間の初日から末日までの期間が二週間以上である場合であって、二週間経過日が
規則第十八条第七項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合、初日請求日から二週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間
6 介護休暇の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。
一部改正〔平成一一年人委告示一号・一四年三号・二二年一号・二八年三号・令和五年二号〕
第十五 介護時間関係
1
条例第十五条の二第一項の「連続する三年の期間」は、
同項に規定する一の継続する状態について初めて介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日を起算日として、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条の例により計算するものとする。
3 第十四の第二項の規定は、職員の介護時間を承認した任命権者と当該職員が所属する給与の支給義務者が異なる場合について準用する。
4 第十四の第八項の規定は、介護時間の請求について準用する。
追加〔平成二八年人委告示三号〕
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成七年四月一日から施行する。
(福井県職員等の休日および休暇に関する条例および福井県職員等の休日および休暇に関する条例施行規則の運用方針の廃止)
2 福井県職員等の休日および休暇に関する
条例および福井県職員等の休日および休暇に関する
条例施行
規則の運用方針(昭和三十一年福井県人事委員会告示第六号)は、廃止する。
附 則(平成九年人委告示第一号)
この告示は、平成九年一月二十日から施行する。
附 則(平成一〇年人委告示第一号)
この告示は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年人委告示第一号)
この告示は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年人委告示第一号)
この告示は、平成十二年三月二十三日から施行する。
附 則(平成一二年人委告示第二号)
この告示は、平成十二年六月十四日から施行する。
附 則(平成一三年人委告示第一号)
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委告示第一号)
この告示は、平成十四年三月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委告示第三号)
この告示は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委告示第四号)
この告示は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委告示第一号)
この告示は、平成十五年二月十四日から施行する。
附 則(平成一六年人委告示第一号)
この告示は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委告示第三号)
(施行期日)
1 この告示は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第十二の第十六項第二号ロの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から引き続き在職する再任用短時間勤務職員の施行日以後の平成十七年における規則第十七条第一項第九号、第十号、第二十号および第二十一号に掲げる場合の特別休暇の期間については、改正後の第十二の第十八項ただし書の規定により定められる日数から施行日前までに取得した休暇日数を減じた日数以内(当該日数が負となるときは、〇日)とする。
附 則(平成一七年人委告示第七号)
この告示は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第六の第一項第五号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年人委告示第一号)
この告示は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一八年人委告示第四号)
この告示は、平成十八年十月二十日から施行する。
附 則(平成一九年人委告示第一号)
この告示は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委告示第二号)
この告示は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委告示第一号)
この告示は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委告示第二号)
この告示は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委告示第一号)
この告示は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委告示第三号)
この告示は、平成二十一年六月十六日から施行する。
附 則(平成二二年人委告示第一号)
(施行期日)
1 この告示は、平成二十二年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示による改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用方針に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二二年人委告示第二号)
(施行期日)
1 この告示は、平成二十二年六月三十日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示による改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用方針に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二二年人委告示第三号)
この告示は、平成二十三年一月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委告示第一号)
この告示は、平成二十三年五月六日から施行する。
附 則(平成二三年人委告示第三号)
この告示は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則(平成二四年人委告示第一号)
この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年人委告示第二号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年人委告示第三号)
この告示は、平成二十四年七月二十四日から施行する。
附 則(平成二五年人委告示第一号)
この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年人委告示第一号)
この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年人委告示第一号)
この告示は、平成二十七年二月二十日から施行する。
附 則(平成二七年人委告示第二号)
この告示は、平成二十七年十二月二十二日から施行する。
附 則(平成二八年人委告示第三号)
この告示は、平成二十九年一月一日から施行する。
附 則(平成二九年人委告示第一号)
この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日人委告示第一号)
この告示は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和三年二月二日人委告示第一号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日人委告示第二号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年一二月二八日人委告示第四号)
この告示は、令和四年一月一日から施行する。
附 則(令和五年一月一九日人委告示第一号)
この告示は、令和五年一月十九日から施行する。
附 則(令和五年三月二二日人委告示第二号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三〇日人委告示第三号)
(施行期日)
1 この告示は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 令和五年旧法 令和三年改正法による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)をいう。
三 令和四年改正定年条例 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年福井県条例第二十九号)をいう。
四 暫定再任用職員 令和四年改正定年条例附則第三条第一項もしくは第二項、第四条第一項もしくは第二項、第五条第一項もしくは第二項または第六条第一項もしくは第二項の規定により採用された職員をいう。
五 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員であって地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務職員の職を占めるものをいう。
六 旧地公法再任用職員 この告示の施行前に令和五年旧法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項または第二十八条の六第一項もしくは第二項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
3 暫定再任用短時間勤務職は、令和五年福井県人事委員会告示第三号の規定による改正後の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用方針(平成七年福井県人事委員会規則告示第一号。以下「改正後の勤務時間等関係運用方針」という。)第十一の第二項および第十六項ならびに第十三の第十一項および第二十二項の規定の適用については、同運用方針第十一の第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員等(第5項において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)とみなして適用し、第十三の第二十二項第二号の規定の適用については、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福井県条例第二号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務時間職員とみなして適用する。
4 令和十七年十二月三十一日までの間における改正後の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成七年福井県人事委員会規則第二号。以下「勤務時間規則」という。)第十二条の二第一項第二号の「人事委員会が別に定める日数」は、改正後の勤務時間等関係運用方針第十一の第七項の規定にかかわらず、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数とする。
一 当該年において、暫定再任用職員等(暫定再任用職員および旧地公法再任用職員のうち、常時勤務を要する官職を占める職員をいう。以下この号および次項において同じ。)に相当する企業職員等(勤務時間条例第十二条第一項第三号に規定する企業職員等をいう。以下この項および次項において同じ。)となった者であって、引き続き暫定再任用職員等となったもの 当該企業職員等となった日において新たに暫定再任用職員等となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じて改正後の勤務時間規則別表第一の日数欄に掲げる日数から、当該年において暫定再任用職員等となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数
二 当該年において、特定再任用職員等(定年前再任用短時間勤務職員、旧地公法再任用職員、暫定再任用職員および勤務時間条例第二条第四項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下この号および次項において同じ。)に相当する企業職員等となった者であって、引き続き特定再任用職員等となったもの(前号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
イ 当該年において、特定再任用職員等に相当する企業職員等から引き続き特定再任用職員等となった場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該企業職員等から引き続き特定再任用職員等となった日において新たに特定再任用職員等となったものとして勤務時間条例第十二条第一項第二号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該企業職員等となった日において当該企業職員等が相当する特定再任用職員等となり、かつ、当該年において特定再任用職員等となった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして同号の規定を適用した場合に得られる日数(次項第二号ロにおいて「特定再任用職員等みなし付与日数」という。)から、同日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数を加えて得た日数
ロ 当該年において、新たに特定再任用職員等となった者(企業職員等から引き続き特定再任用職員等となった者を除く。)から引き続き特定再任用職員等に相当する企業職員等となり、当該企業職員等から引き続き特定再任用職員等となった場合 イに定める日数に、当該企業職員等となった日の前日における年次休暇の残日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を加えて得た日数
5 令和十七年十二月三十一日までの間における改正後の勤務時間規則第十二条の二第四項第二号の「人事委員会が別に定める日数」は、改正後の勤務時間等関係運用方針第十一の第九項の規定にかかわらず、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数とする。
一 当該年の前年に特定再任用職員等に相当する企業職員等であった者であって、引き続き当該年に特定再任用職員等となったもの 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
イ 当該年の初日に特定再任用職員等となった場合 特定再任用職員等となった日において新たに特定再任用職員等となったものとして勤務時間条例第十二条第一項第一号または第二号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該年の前年における年次休暇に相当する休暇の残日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とし、当該日数が当該年の前年における当該企業職員等として在職した期間を当該企業職員等が相当する特定再任用職員等として在職したものとみなして勤務時間条例第十二条第一項第一号または第二号の規定を適用した場合に得られる日数を超えるときは、当該日数。ロにおいて同じ。)を加えて得た日数
ロ 当該年の初日後に特定再任用職員等となった場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
(イ) 暫定再任用職員等に相当する企業職員等から引き続き当該年の初日後に暫定再任用職員等となった場合 当該年における暫定再任用職員等に相当する企業職員等に相当する企業職員等として在職した期間を当該企業職員等が相当する暫定再任用職員等として在職したものとみなして勤務時間条例第十二条第一項第一号または第二号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該年の前年における年次休暇に相当する休暇の残日数を加えて得た日数から、当該年において暫定再任用職員等となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数
(ロ) (イ)に掲げる場合以外の場合 当該年において特定再任用職員等となった日において新たに特定再任用職員等となったものとして勤務時間条例第十二条第一項第二号の規定を適用した場合に得られる日数(次号において「基本日数」という。)に、当該年の初日において特定再任用職員等となり、かつ、当該年において特定再任用職員等となった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして同号の規定を適用した場合に得られる日数と当該年の前年における年次休暇に相当する休暇の残日数とを合計した日数から、同日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数を加えて得た日数
二 当該年の前年に特定再任用職員等であった者であって、引き続き当該年に特定再任用職員等に相当する企業職員等となり、当該企業職員等から引き続き特定再任用職員等となったもの 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
イ 当該年の初日に特定再任用職員等に相当する企業職員等となった場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
(イ) 暫定再任用職員等であった者から引き続き当該年の初日に暫定再任用職員等に相当する企業職員等となり、当該企業職員等から引き続き暫定再任用職員等となった場合 当該年における暫定再任用職員等に相当する企業職員等として在職した期間を当該企業職員等に相当する暫定再任用職員等として在職したものとみなして勤務時間条例第十二条第一項第一号または第二号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該年の前年における年次休暇の残日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数。以下この号において同じ。)を加えて得た日数から、当該年において暫定再任用職員等となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数
(ロ) (イ)に掲げる場合以外の場合 基本日数に、当該年の初日において特定再任用職員等となり、かつ、当該年において特定再任用職員等となった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして勤務時間条例第十二条第一項第二号の規定を適用した場合に得られる日数と当該年の前年における年次休暇の残日数とを合計した日数から、同日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数を加えて得た日数
ロ 当該年の初日後に特定再任用職員等に相当する企業職員等となり、当該企業職員等から引き続き特定再任用職員等となった場合 基本日数に、当該年の初日において特定再任用職員等となり、かつ、当該年において企業職員等となった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして勤務時間条例第十二条第一項第二号の規定を適用した場合に得られる日数、特定再任用職員等みなし付与日数および当該年において特定再任用職員等となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数および使用した年次休暇の日数から、当該年において特定再任用職員等となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数および使用した年次休暇の日数(これらの日数に一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数
6 暫定再任用職員に対する改正後の勤務時間等関係運用通知第十一の第十項の規定の適用については、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、同項の規定を適用する。
附 則(令和五年一二月二六日人委告示第五号)
この告示は、令和六年一月一日から施行する。
附 則(令和六年三月三一日人委告示第一号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第十一関係)
在職期間 | 日数 |
当該職員が年を通じて在職するものとみなした場合の規則第十二条に規定する日数 |
一日 | 二日 | 三日 | 四日 | 五日 | 六日 | 七日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 | 十二日 | 十三日 | 十四日 | 十五日 | 十六日 | 十七日 | 十八日 | 十九日 | 二十日 |
一月までの期間 | 〇日 | 〇日 | 〇日 | 〇日 | 〇日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 |
一月を超え二月までの期間 | 〇日 | 〇日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 | 三日 | 三日 | 三日 |
二月を超え三月までの期間 | 〇日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 | 三日 | 四日 | 四日 | 四日 | 四日 | 五日 | 五日 | 五日 |
三月を超え四月までの期間 | 〇日 | 一日 | 一日 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 | 四日 | 四日 | 四日 | 五日 | 五日 | 五日 | 六日 | 六日 | 六日 | 七日 |
四月を超え五月までの期間 | 〇日 | 一日 | 一日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 五日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 | 七日 | 八日 | 八日 | 八日 |
五月を超え六月までの期間 | 一日 | 一日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 | 七日 | 八日 | 八日 | 九日 | 九日 | 十日 | 十日 |
六月を超え七月までの期間 | 一日 | 一日 | 二日 | 二日 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 | 八日 | 八日 | 九日 | 九日 | 十日 | 十一日 | 十一日 | 十二日 |
七月を超え八月までの期間 | 一日 | 一日 | 二日 | 三日 | 三日 | 四日 | 五日 | 五日 | 六日 | 七日 | 七日 | 八日 | 九日 | 九日 | 十日 | 十一日 | 十一日 | 十二日 | 十三日 | 十三日 |
八月を超え九月までの期間 | 一日 | 二日 | 二日 | 三日 | 四日 | 五日 | 五日 | 六日 | 七日 | 八日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 | 十一日 | 十二日 | 十三日 | 十四日 | 十四日 | 十五日 |
九月を超え十月までの期間 | 一日 | 二日 | 三日 | 三日 | 四日 | 五日 | 六日 | 七日 | 八日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 | 十二日 | 十三日 | 十三日 | 十四日 | 十五日 | 十六日 | 十七日 |
十月を超え十一月までの期間 | 一日 | 二日 | 三日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 | 十二日 | 十三日 | 十四日 | 十五日 | 十六日 | 十七日 | 十七日 | 十八日 |
十一月を超え一年未満の期間 | 一日 | 二日 | 三日 | 四日 | 五日 | 六日 | 七日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 | 十二日 | 十三日 | 十四日 | 十五日 | 十六日 | 十七日 | 十八日 | 十九日 | 二十日 |
全部改正〔平成一七年人委告示三号〕、一部改正〔平成二二年人委告示一号〕
 様式第一号
様式第一号(第一関係)
追加〔令和5年人委告示2号〕
 様式第二号
様式第二号(第一関係)
追加〔令和5年人委告示2号〕
 様式第三号
様式第三号(第一関係)
追加〔令和5年人委告示2号〕
 様式第四号
様式第四号(第四関係)
全部改正〔平成22年人委告示2号〕、一部改正〔令和3年人委告示2号・5年2号〕
 様式第五号
様式第五号(第七関係)
全部改正〔平成22年人委告示1号〕、一部改正〔令和3年人委告示2号・5年2号〕
 様式第六号
様式第六号(第十三関係)
追加〔平成22年人委告示1号〕、一部改正〔令和3年人委告示2号・5年2号〕