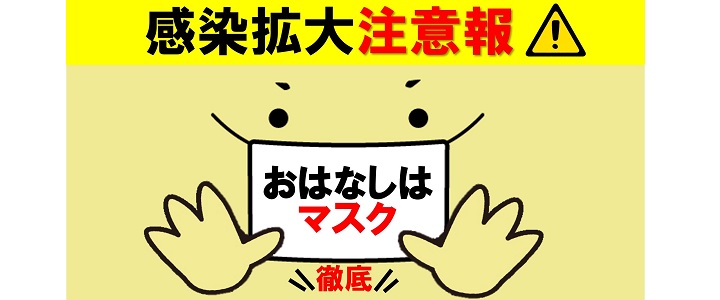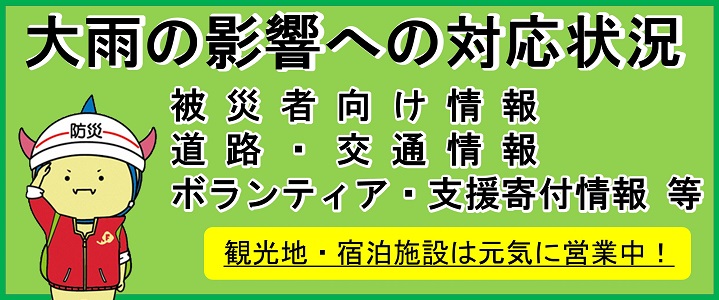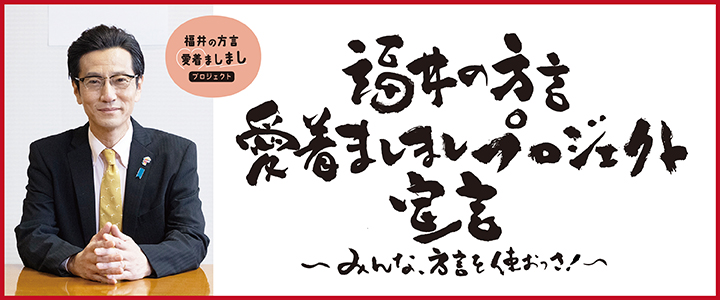関西大学での講義「都市と地方を考える~ふるさとの発想~」
|
このページは、平成20年12月8日(月)、「都市と地方を考える~ふるさとの発想~」という演題により、関西大学千里山キャンパスで行われた知事の講義概要をまとめたものです。 |
|
【Ⅰ 関西大学との交流】 関西大学とは様々な分野で連携が始まっており、今年8月には福井市で関西大学の「法律相談所」の学生(25人)とOBの弁護士、相談所の顧問の先生により、無料法律相談を実施していただきました。 さらに、昨年の12月には、本大学で「笑い」について研究されている社会学部の木村洋二教授に福井においでいただき、「関大ふくい笑い講」を開催しました。 さて、今年は、いろいろな意味で、福井県が話題になった年です。 「笑い」ばかりだと思われると困るので、その他の受賞理由もご紹介します。 さて、みなさんは政策創造学部の学生ですから、今回の講義では、企業や自治体に就職する際に役に立つようなことをできるだけ多く話したいと思います。例えば、公務員の面接では、その自治体の課題や政策を勉強しておくことはもちろんですが、その自治体に対する自分の思いや考えを自分の言葉で話をすることも大切なことだ、というようなことです。 |
|
【Ⅱ テーマ】 今日の講義で、皆さんに伝えたいことは三つあります。 二つ目は、地方は都市に依存しているのではないということ、さらに言うと、実は、これまでずっと地方が都市を支えてきた、ということを知って欲しいということです。 三つ目は、日本全体として活力のある国を作っていくために、地方自治体の役割が大きくなっていくだろう、ということを申し上げたいと思います。 今から話をする「ふるさと納税」や「道州制」は、「都市と地方」、「地方分権」、「地方財政」、「日本の国の形」など様々な論点が詰まっており、勉強するには格好の材料となるので、よく聞いて参考にしていただいて、自分の考えを整理して、自分の考えを持っていただきたいと思います。 |
|
【Ⅲ 多様な見方】 まず、皆さんには、自分が生まれ育った時代がどのようなものであるかを考えてみてほしいと思います。 みなさんは、このような時代を当り前のものとして捉えていると思います。政治・マスコミ・大学が言っていることや街の風景などは、ずっと以前からこのような雰囲気だと思うかもしれませんが、実はそうではなくて、この20年間で起こったことなのです。そのような見方をしてみたいと思います。 都市と地方の格差もあらわれ、特に小泉内閣後は、地方と都市の格差是正、ニート、フリーターの問題などがきっかけとなり、時代は変わり始めています。 時間というものを当り前と思わないで、多様に見てほしいと思います。ここ10年、20年の歴史でもこのようなことがいえるので、人類の長い歴史の上ではそれぞれの風潮があるということ、また、みなさんはこれからの日本と歴史を変えられる立場にあるという気持ちを持ってほしいと思います。 次に、地理の観点からも多様な見方をしてみたいと思います。 現在、大阪府の人口は約880万人です。また、大阪市は260万人、大阪市に次いで2006年に政令指定都市となった堺市は82万人です。つまり、大阪府の人口の多くは政令指定都市の人口ということになります。ちなみに福井県の人口は83万人です。 さらに、福井県の状況というと、勤労者世帯1世帯当たりの貯蓄現在高も全国第1位であり、持ち家住宅1軒当たり延べ床面積は全国2位、共働き率は全国1位です。 このような状況を見ると、地理の観点からも一概に大きいから良くて、小さいから悪いといえないということが分かると思います。 また、人物の話をしますと、幕末の頃、現在の大阪の中央区に「適塾」があり、そこで、越前藩士の橋本左内が学んでいました。 昔から、地方の人材が日本を支えています。都市と地方の関係は、それぞれの地方で育った優れた若者が、都市に集まって交流し、新しい考えを見つけ、鍛えて日本の発展につなげていくという、両輪の関係にあったといえます。俗に言われるように「田舎者が勝って、日本を作った」のです。 |
|
【Ⅳ 地方が都市を支えている】 電気だけではありません。水もまた同じように、関西圏の人口は約2000万人ですが、このうち1400万人は、その飲料水を琵琶湖に依存しています。 このように、大阪を含めた大都市が独立して存在しているわけではありません。福井県、滋賀県などの地方が都市のエネルギーや水などの基本的なライフラインを支えているから成り立っているのです。 都市にある大学も、学生の多くは地方出身者であり、そのような意味では大学も地方が支えているといえます。場合によっては、親元からの仕送りがあり、それが大学の周辺の町で消費され、その街さえも支えているということにもなります。 このように考えると、財政学において、「地方交付税は地方にそんなに回すべきではない」とか、「都市で集中して使えばいいのだ」とかという議論がありますが、そんなに単純なことではないということも分かると思います。 租税に関しても、明治時代初期の国税収入はおよそ3分の2(多いときには9割)が地租でした。最大の納税地域は新潟県と北陸地方(富山県、石川県、福井県)でした。当時の国の富の源泉は地方にあったのです。 そのような歴史の中で、だんだん時代が変わってきました。戦後の高度経済成長期には、多額の予算が太平洋側に投入されました。これが、現在の日本の姿を形づくったものです。 現在、東京への一極集中が問題となっています。大阪も例外ではなく、人口の流出が目立っています。日本の二大都市として大阪が復活するためには、北陸新幹線のような高速交通ネットワーク体系で地方と大阪を結ぶ必要があると思っています。そのためにも、大阪の方には、北陸新幹線を大阪まで結ぶために、一緒に行動を共にしていただきたいと思っています。 |
|
【Ⅴ 地方自治体の役割(ふるさと納税)】 福井県で成長する若者が出生から高校卒業までに受ける行政サービスの総額は、1人当たり約1800万円になります。ざっと計算して数百億円規模の公的な支出が大都市へと流出しているのと同じことになります。 私は、日本全体がこのような状況ではいけないと思い、平成18年に「ふるさと納税」を提案しました。そのときの考えの基本になったのが、このライフサイクル・バランスです。 「ふるさとの納税」の仕組みを知っていますか。簡単にいうと、自分が納税(寄付)したい自治体を選んで寄付をすると、現在住んでいる自治体からはその分だけ税金が控除されるというものです。納税すべき総額は基本的に変わりません。 明治以来、日本では、自分の意思で税金の納付先を決めることはできませんでした。全て強制的に法律に書かれたところへ納めることになっていました。 自治体も、自分たちもしっかりした政策を行わないと、自分の自治体を選択してもらえないということになります。さらに、そこの住民の方も他の自治体に寄付をしてしまうという事態も生じうるということです。 さらに、「ふるさと納税」の可能性をお話したいと思います。 日本は、「寄付」という観念が非常に低い国です。日本での年間の寄付の総額は全て合計しても数千億円にしかなりません。米国などに比べると桁が違うほど非常に少ない額です。 それで、日本に寄付文化を定着させていく必要があるのだろうと思います。 ボランティアも大事です。阪神・淡路大震災からボランタリズムというものが、日本に普及しました。ボランティアは労力の寄付といえるでしょう。 福井県では、平成16年に福井豪雨を経験しました。その際に、ある人から、宝くじの当選券が匿名で送られて来ました。それは2億円の当選宝くじだったのです。私はその時に、日本には困った時に助け合う心がある、また、それを一歩進めて、日本に寄付文化を広める必要があると思ったわけです。 「ふるさと納税」はみなさんが学ぶ、地方自治、民主主義、税金、投票、新しい公という問題を内在していますので、研究の対象としてほしいと思います。 また、社会人になったら、ぜひ自分のふるさとに寄付してください。これからも続く制度ですので、自分たちのふるさとを応援してほしいのです。 さらに大事なことは、社会人になるのをきっかけに、また、定年してからふるさとに戻るような社会をつくらなければならないと思っています。また、我々も、戻りたくなるふるさとをつくる努力をしなければならないと思っています。 |
|
【Ⅵ 道州制】 私は、この道州制に不賛成であります。 発行する紙幣に対して同等の金を保有し、金と紙幣との兌換を保障する制度を金本位制といいます。戦前、主要国のほとんどが金本位制を採用していましたが、日本は当時、一時的にこれから離脱していました。しかし、金の輸出入の解禁(金解禁)によって、金本位制に復帰するようもとめる声が国内外で支配的になり、そのため、1930年1月に日本政府は金解禁に踏み切りました。折りしもその前年、ニューヨーク株式市場の株価大暴落に端を発した世界恐慌が起こり、日本経済は大打撃を受けることになります。日本は、1931年に再び金輸出を禁止しましたが、金解禁によって約2ヶ月の間に、現在の価値で約9兆円もの金貨を国外に流出してしまったと言われています。 金解禁は、当時、誰もが賛成した施策ですが、現在の評価は大きく異なります。このように世界中に大きな影響を与えるような政策であっても、必ずしも多面的な観点から分析したり、みんながじっくりと考えているわけではなく、周りの雰囲気で賛成したり、反対をしていることもあります。このような事例は多いと思います。 みなさんも、一般的に言われている事柄に簡単に賛成しないでください。自分の考えを持って、よく見てほしいのです。 今回の道州制の議論は、都道府県を廃止して11か12の広域的な道州にするというものです。 また、経済活動が国の制約から解放され、産業が強くなるという議論に対しては、「日本の企業や地場産業は大きな打撃を受けることになる。」と思います。現在のグローバルの時代に、道州が他の国と対等に貿易をして勝てるとは思いません。日本全体で経済政策をつくり、景気対策をしなければ、日本は他の国にたちうちできないと思いますし、景気も回復しないと思います。 二重行政の解消や行政がスリム化するという議論についても、「行政機構は肥大化する」と考えます。 |
|
【Ⅶ 最後に】 地方では、住民の生活の実情を知る地方自治体こそが適切な対策を立て、実行することができます。結局、住民の生活、つまりふるさとを最後に守ることができるのは自治体だけだと思います。地方分権の本当の理由もここにあるのです。 人々の命と暮らしを守り、ふるさとのつながりを支えるところに、地方自治の本領があると思います。 私は、このふるさとをつくり、守っていくのが自治体の一番の仕事であり、一つひとつのふるさとが良くなることこそ、日本全体を良くすることだと考えています。 |
|
[質疑応答] 学生: 学生: |
お問い合わせ先
(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)