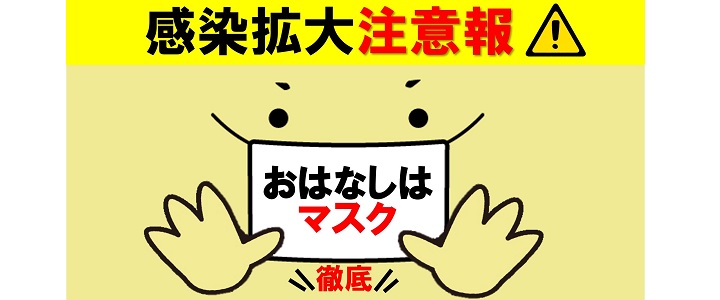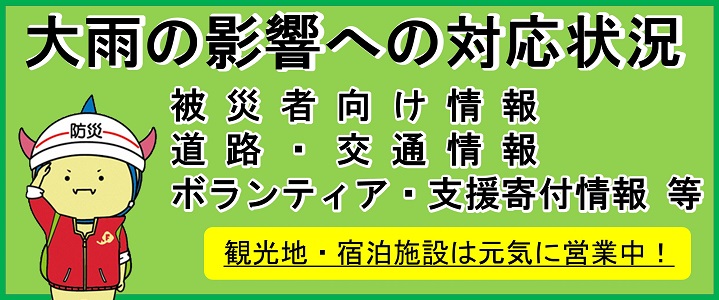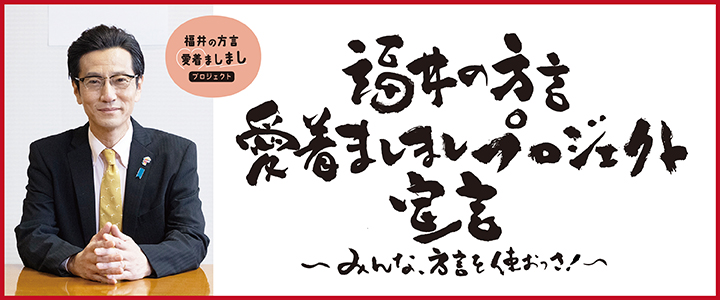日本自治学会 共通議題Ⅱ「道州制」パネルディスカッションでの知事発言要旨
|
このページは、平成19年11月4日(日)、地方分権と地方自治について研究する日本自治学会に、共通議題Ⅱ「道州制」のテーマで知事がパネリストとして参加した際の発言概要をまとめたものです。 |
|
|
|
道州制を考える場合に、現在の都道府県の様子がどのようなものかというのを一度客観的に見ていただくのがよろしいかと思います。 まず1点目は、県境を越える活動がどのような状況か、といったものです。県外への通勤・通学の機会が多いのは主に大都市圏でありまして、奈良県だと3割ですね。日本の平均が8.5%ですが、これを超えるのは9府県に集中しております。 2点目に、都道府県が小さいかどうかということ、大きいことは良いことかということでございます。 3点目は、中心都市への一極集中の可能性についてです。北海道で道州制の特区をやっておりますが、北海道と九州の昭和55年から平成17年までの状況で、北海道は札幌に、九州では福岡にどのくらい人口が集中するかと言いますと、やはり北海道は周辺部の人口が減少しております。他に核となる都市がありませんとどうしても中心地域に人が集まり、周辺部が寂れる傾向があるかもしれない、と一つの例として挙げさせていただきました。 最後に4点目は、都道府県に対する県民の愛着がある、ということでございまして、アイデンティティや愛郷心というものがあることを忘れてはなりません。福井県では、今年の7月に東京、大阪、名古屋、福井でそれぞれ各350名、合計で1,400名の方にアンケートをさせていただきました。道州制に関する福井県独自のアンケート結果です。道州制の導入に反対が57.2%、賛成2割、わからない2割です。反対の理由ですね、つまり今の都道府県がいいんだという理由かも知れませんが、愛着や親しみがあるから、きめ細かな行政ができなくなるから、地方分権につながるとは限らないからということでございます。 都道府県のスケール、それから人々の思いというのは、大体こういうところではないかと思います。 |
|
まず、賛成的なお考えの方の意見です。今の都道府県では分権社会には小さいという意見、経済圏や通勤圏、広域的な課題に道州制だと対応できる。それから、自立的な圏域が形成される。もう公共施設をフルセットで整備するだけの投資ができないから道州で対応する。行革のために道州制を導入すべき。これが賛成のご意見です。 今年1月に入りまして、全国知事会で「道州制に関する基本的な考え方」を整理しておりますが、「まず道州制の導入ありき」ではなくて、「もし、将来道州制を導入するのであれば」という仮定の下で7つの基本原則と8つの具体的検討課題をまとめたのであります。どのようなことが論点・課題となり、地方にとって、どのような視点が必要だろうかといったことを整理しようということです。 この知事会の中でも、北陸地方は、どちらかというと消極的な知事が多かったかと思います。日本列島改造論とか首都機能移転問題などがありましたが、枠組みで物事を議論していきますと、本来理想として描いたものが、一方的になるというのが日本の地方政治、あるいは民主政治だと、残念ながら思うわけでありまして、「道州制ありき」という議論も、そうならないよう、まず地方分権改革を進め、行革、大都市問題の解決が必要かなと思います。 |
|
(問)道州制の導入により、農村の疲弊が解決できるか (問)行革の観点から見て、道州制をどのように考えるか (問)市町村合併で県の役割は変わったか |
お問い合わせ先
(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)