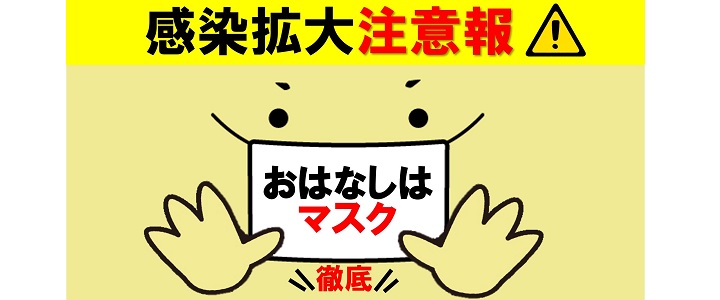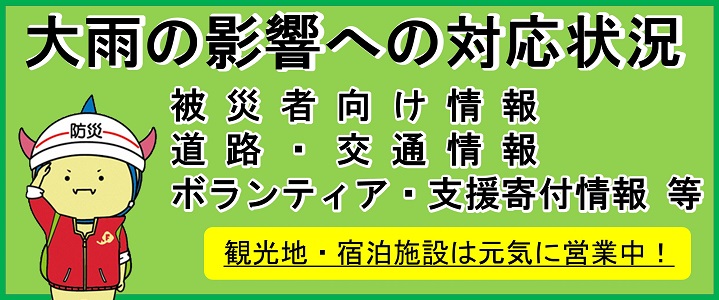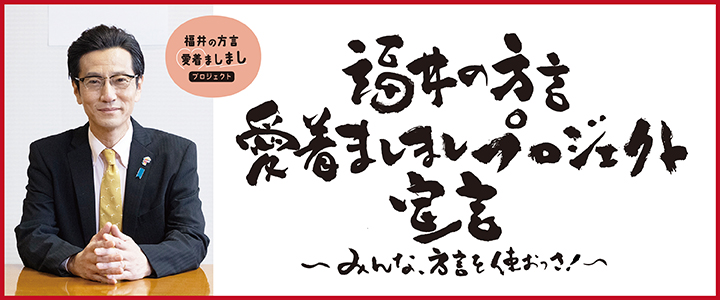全国自治体政策研究交流会議パネルディスカッションでの知事発言要旨
|
このページは、平成20年8月21日(木)、盛岡市民文化ホールで行われた全国自治体政策研究交流会議での知事の発言部分の趣旨を要約したものです。大会には、自治体学会会員、自治体職員など約700人が参加し、「分権時代における地方の自立」をテーマとしてパネルディスカッションが行われました。 |
|
【Ⅰ 地方分権改革について】 マニフェストについては北川先生(北川正恭 早稲田大学大学院教授)からアドバイスをいただきましたが、当時、マニフェストで選挙をしてよかったと思っています。これによって、住民のみなさんとの関係や議会との関係など様々な点で、わかりやすい政治ができていると思います。 そこで、コーディネーターの青山さんから問題提起のあった最近の全国知事会の動きですが、三位一体の改革に対しては期待が大きく全国の知事の議論も活発でした。しかし、結果としてまったく十分な成果があがっていないということで、いまのように元気がなくなっているということかもしれません。 そこで、私の考えを数点申し上げます。 2点目は、できることから地方が提案し、実行に移すということであります。私は、「ふるさと納税制度」という新たな税制を提案し、この5月から全国で実施されています。特に、知事という存在は、国と基礎的自治体の間にあるため、地方自治のことを政府に訴えうる立場にあると思います。私も、なんとかして地方発の制度改正ができないかと思案し、実行に移すことができました。 最後に3点目ですが、地方自治や地方分権は永遠の課題であり、絶えず手を緩めずに努力することが必要です。そして、ここ数年のように一定の(議論の)政治的な山をつくっていくというか、政治運動、分権運動のようなものが必要だと思います。 |
|
【Ⅱ 政治主導の分権改革について】 全国の首長の活動がどれくらい有権者に支持されているかということが新聞などに掲載されたりしますが、知事や市町村長が支持されると議会も支持されますし、また、議会が支持されないと首長も支持されないという結果が出がちだと思います。 その一つの分野としては、新しい計画やプロジェクトなどについて、議会がチェックし問題点を指摘することも重要ですが、平常時でも継続的に議会や行政が一緒になって勉強して取り組んでいくことが大事であり、それが住民の期待でもあると思います。単純に形式的な良し悪しの議論をするだけでは地域はよくなりません。そういう分野が、新しいフロンティアではないかと思います。 議会自体が、組織なり仕事の進め方なりを見直すことも必要だと思います。 |
|
福井県の場合は、地方政府という意味で、福井県政府と言っています。自分たちでできることはする、他の自治体によい影響を及ぼすこと、国の制度の改革につながることなどを言う、通常やるべき仕事に加えて、改善していくという心構えで仕事を進めています。 次の時代の新しい公共サービスとして、具体的に考えている分野についてですが、ひとつ例を挙げますと、これからは農業問題が重要だと思っています。環境や教育、福祉、高齢化対策と関連付けて農業問題にいかに対処するかが新しい分野の例だと思っています。 |
|
【Ⅳ 終わりに】 |
お問い合わせ先
(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)