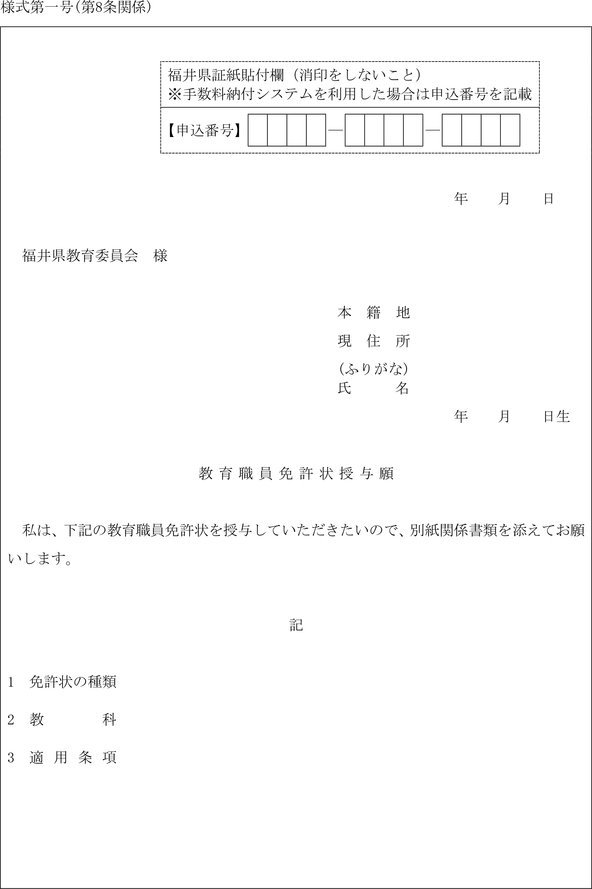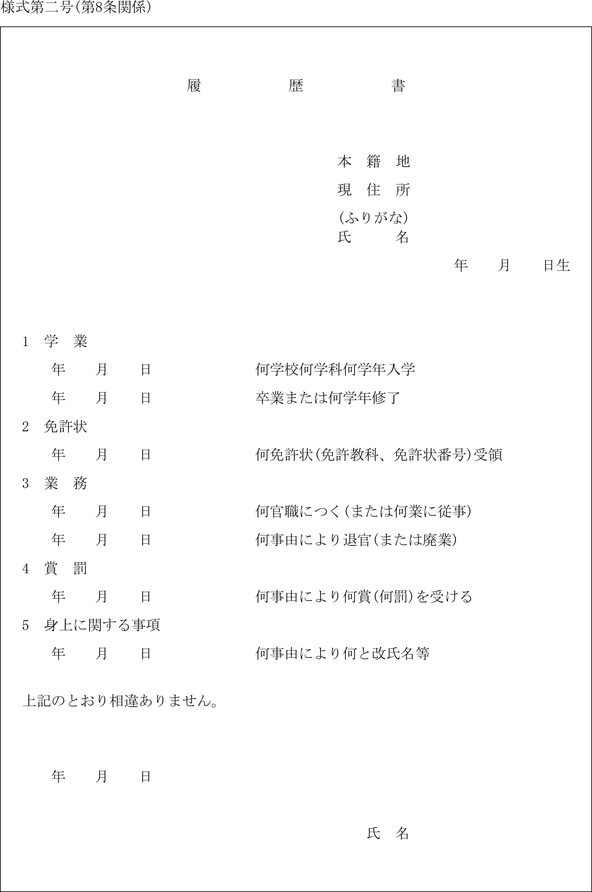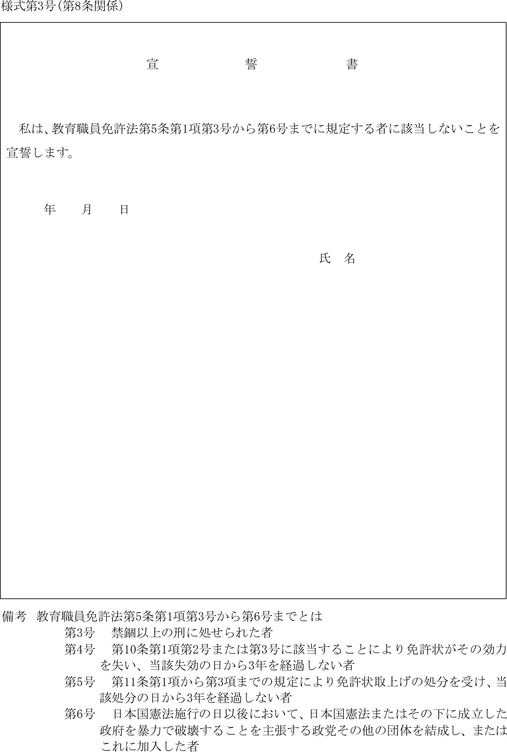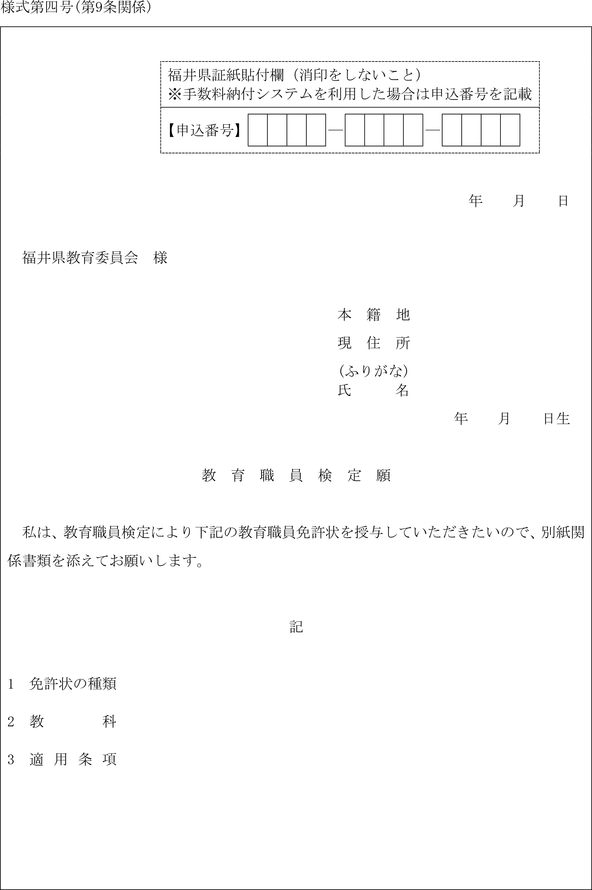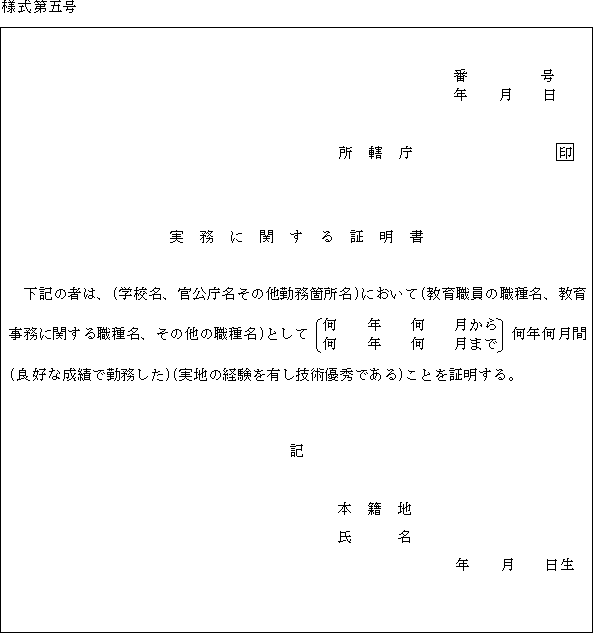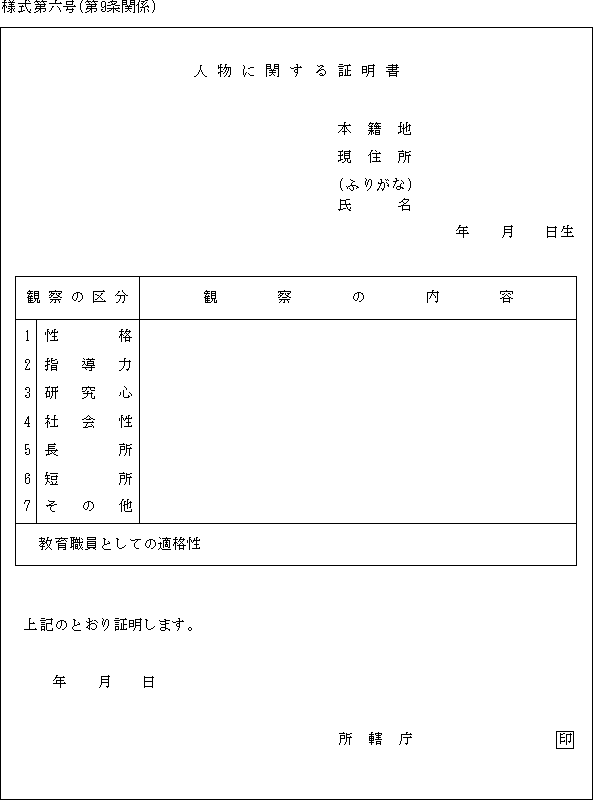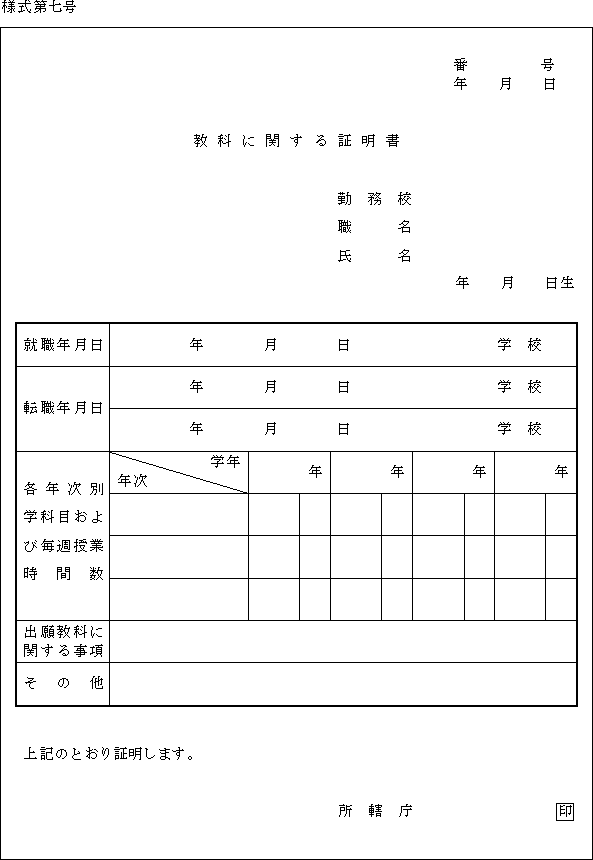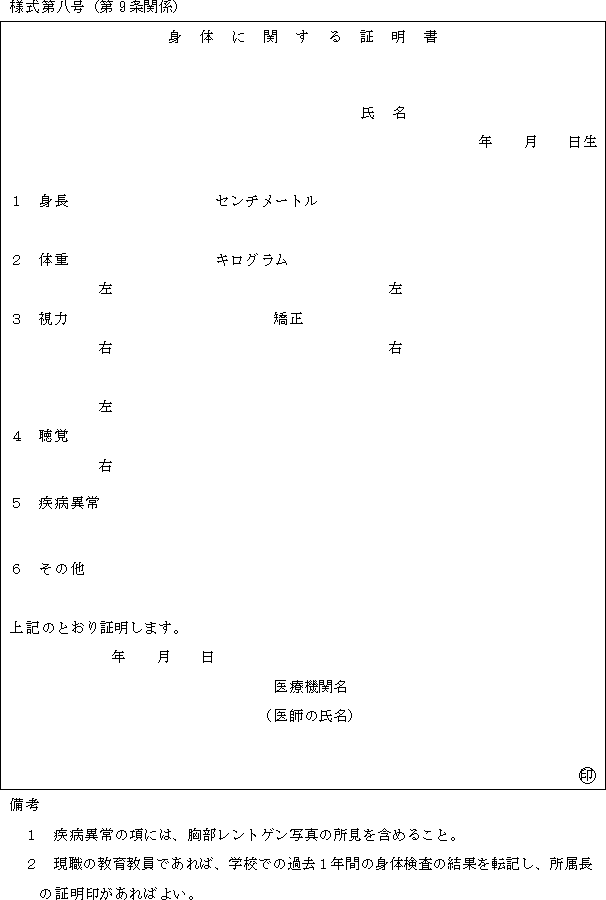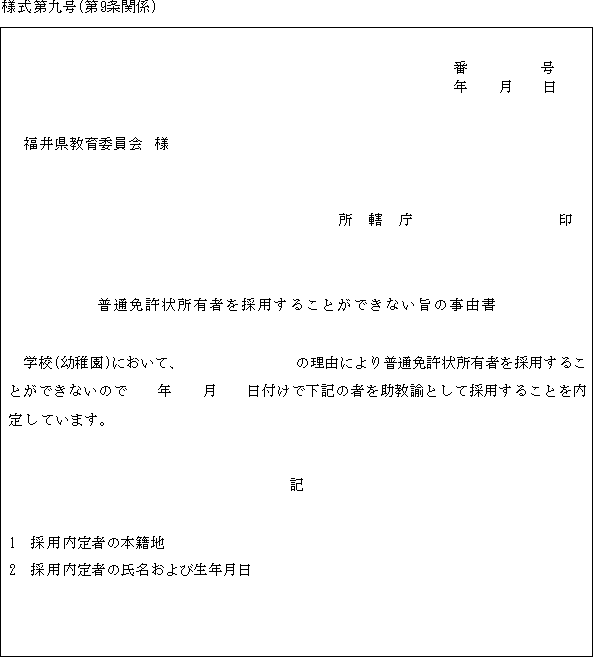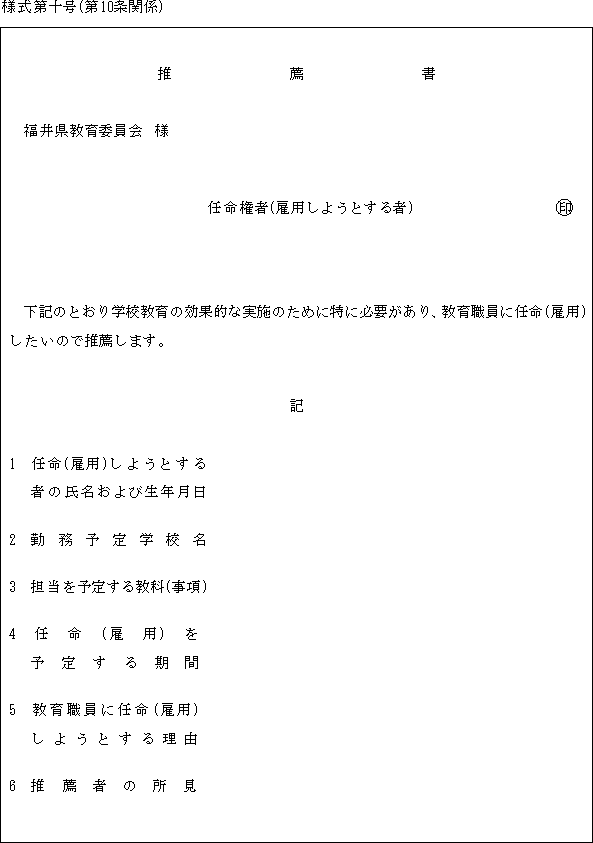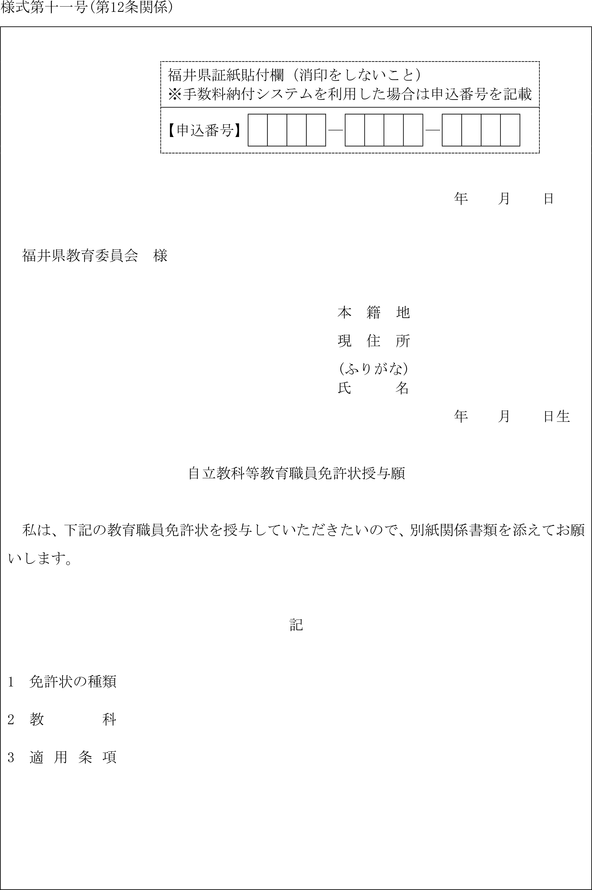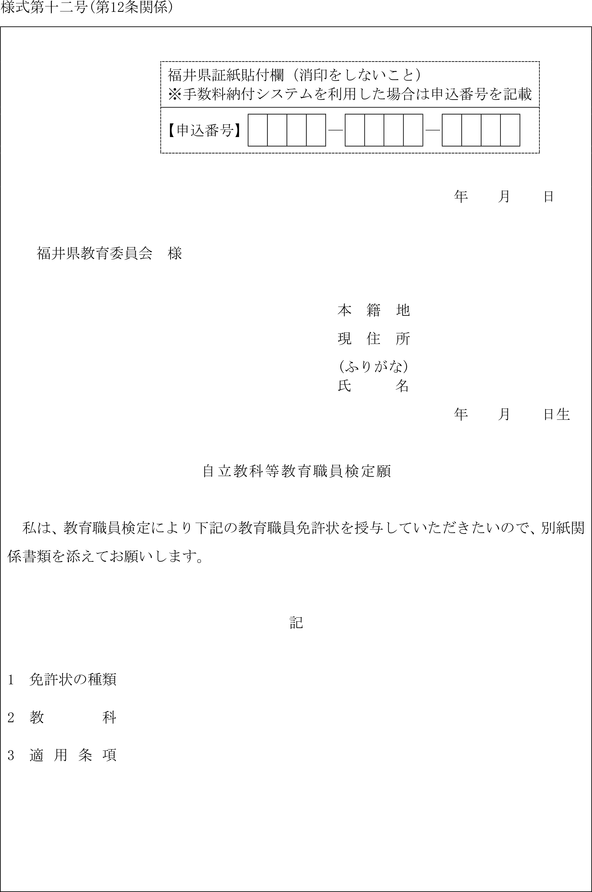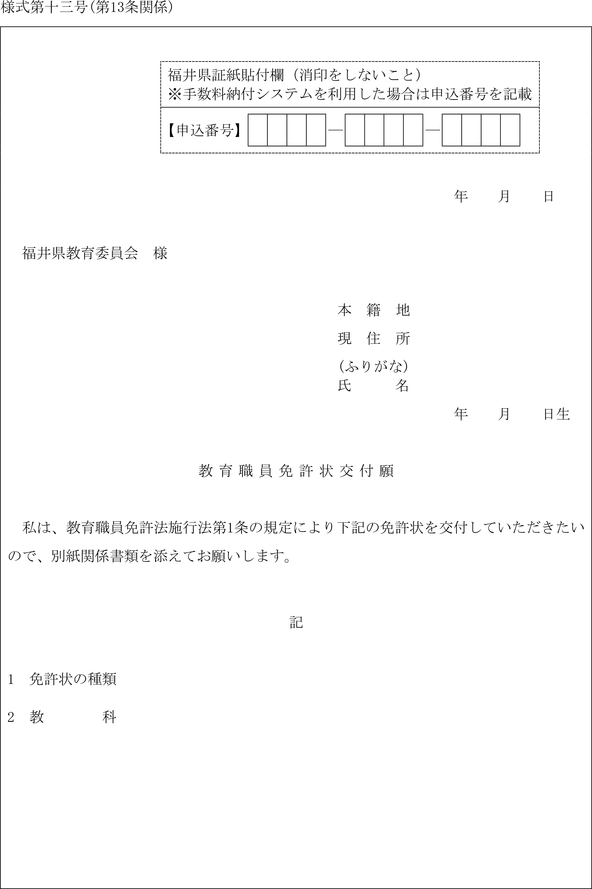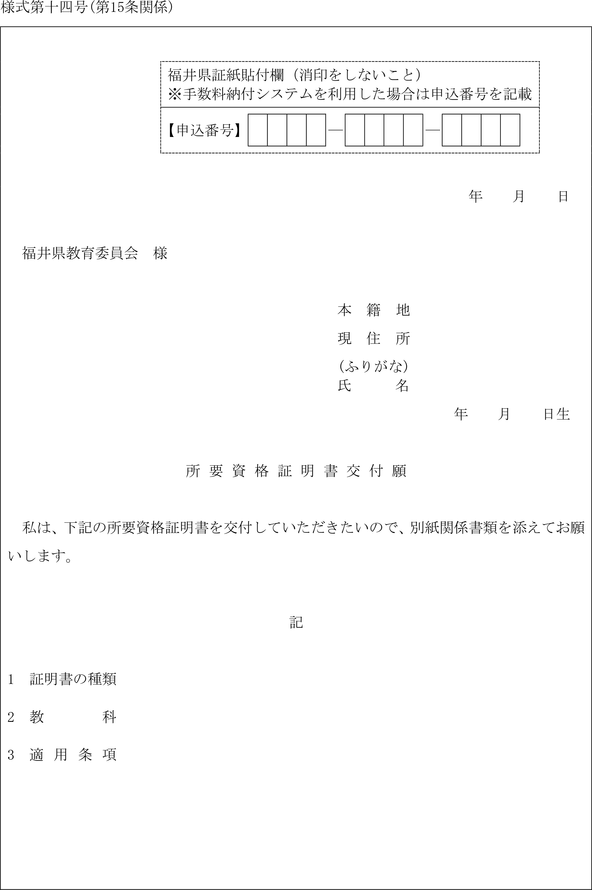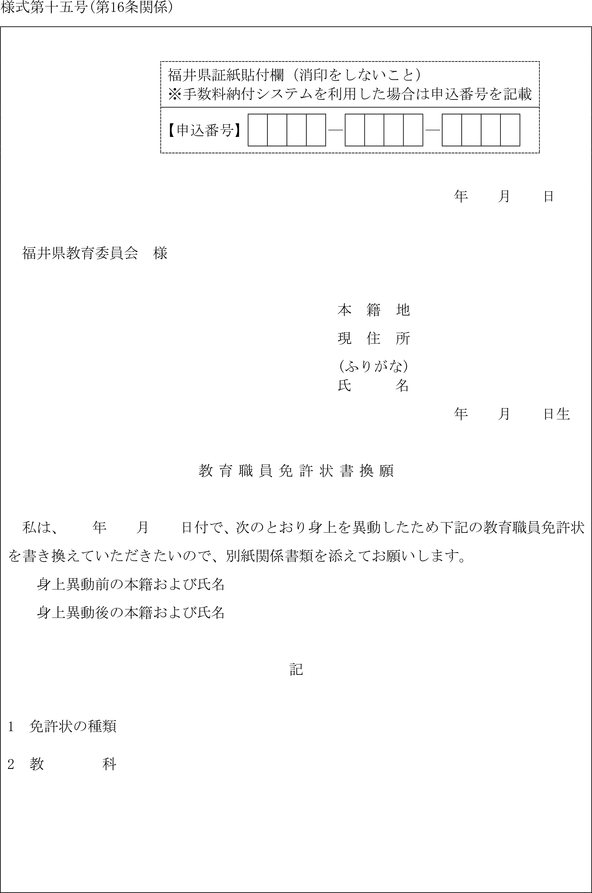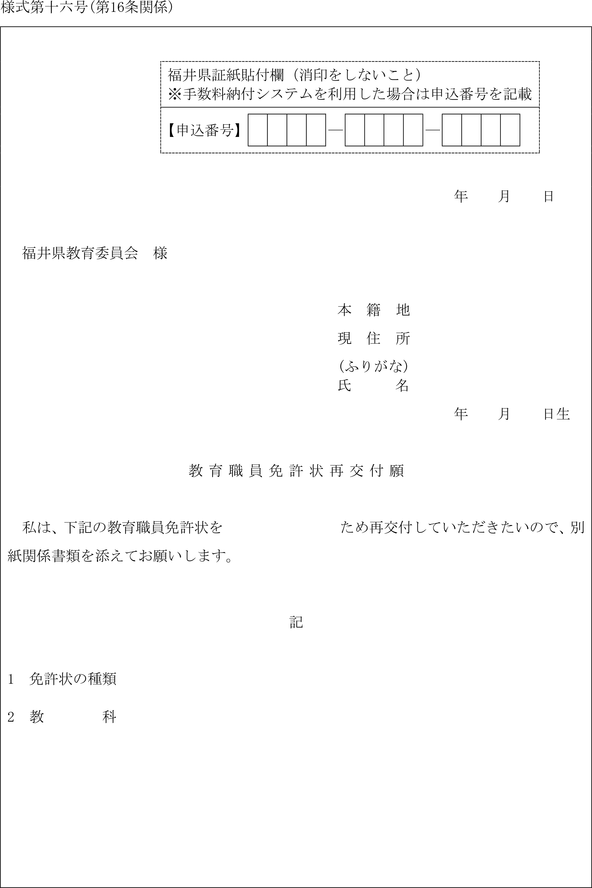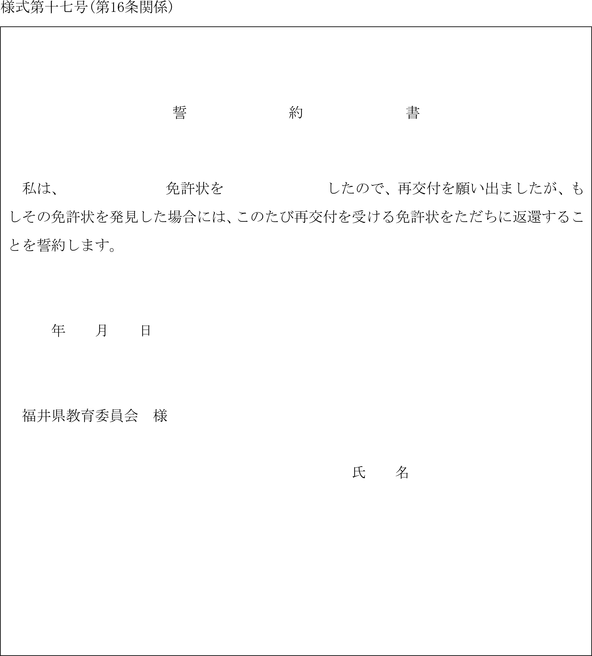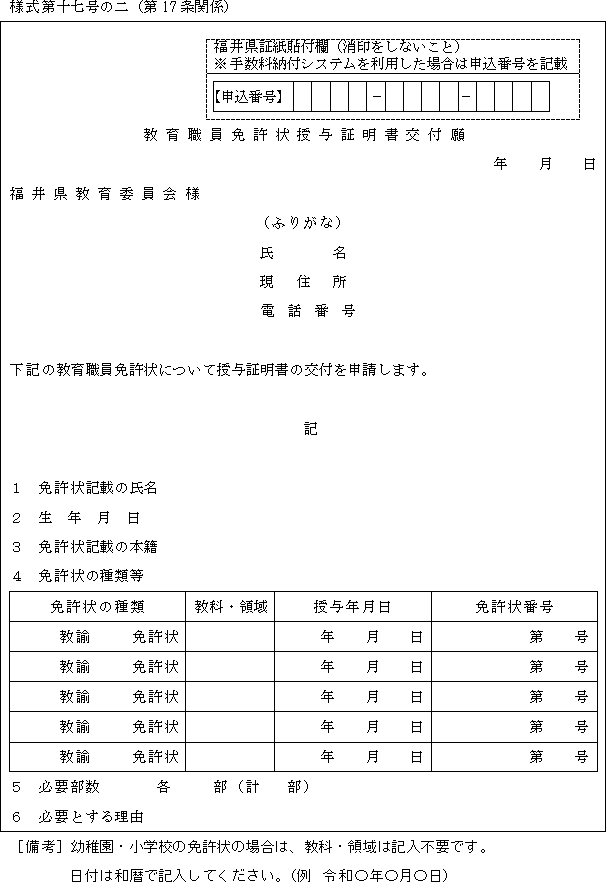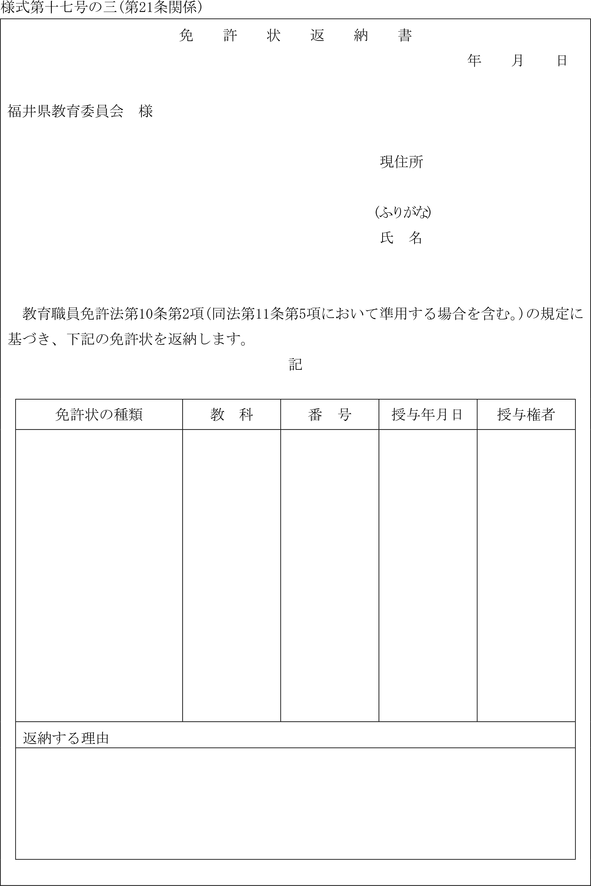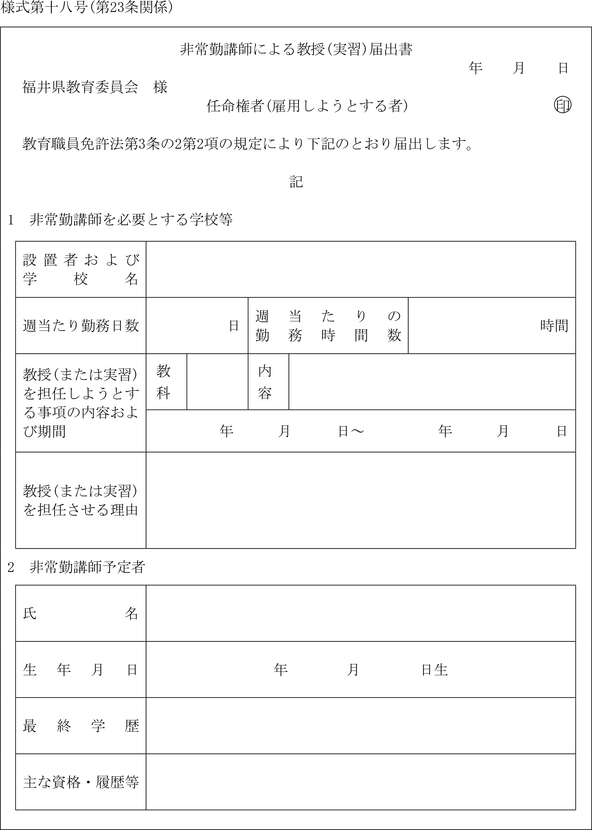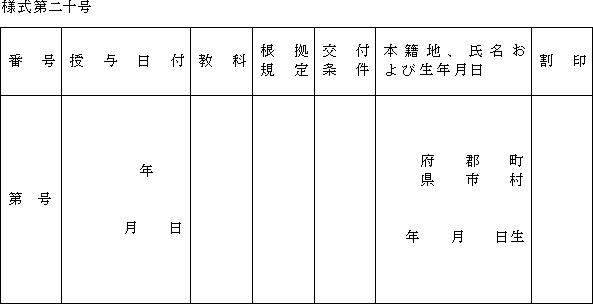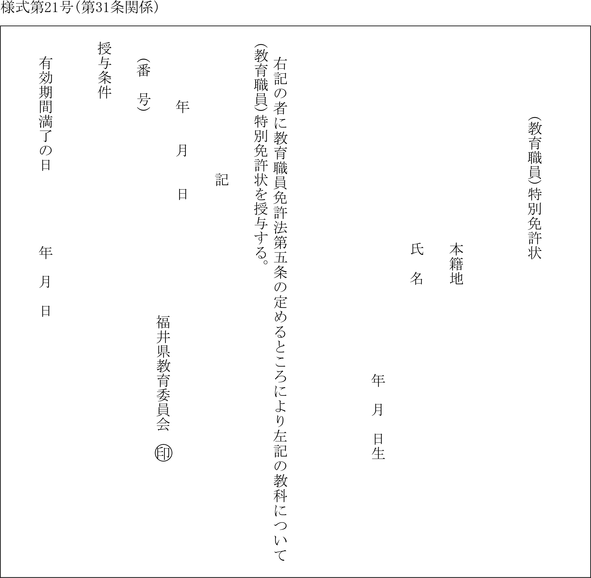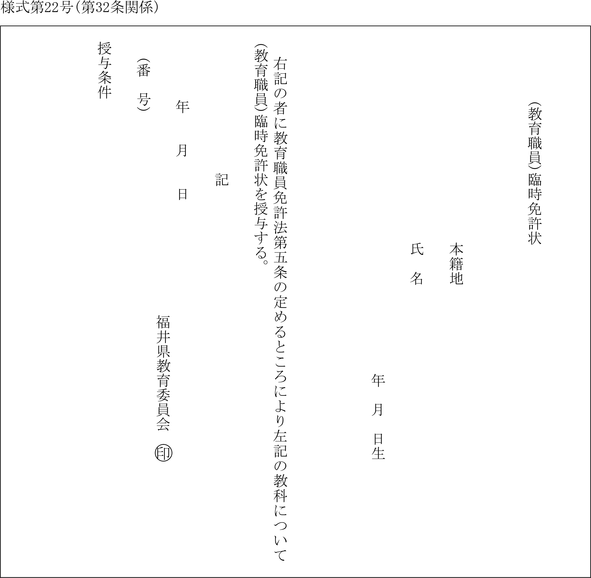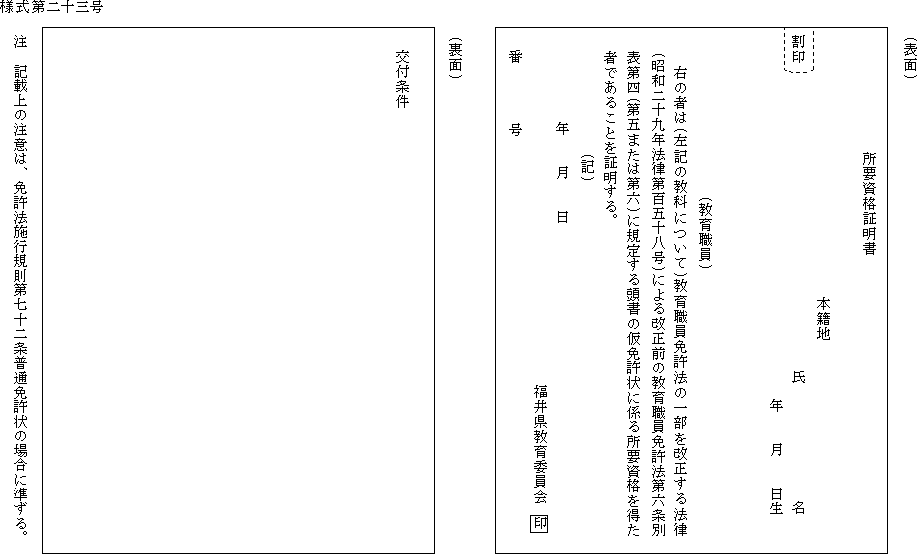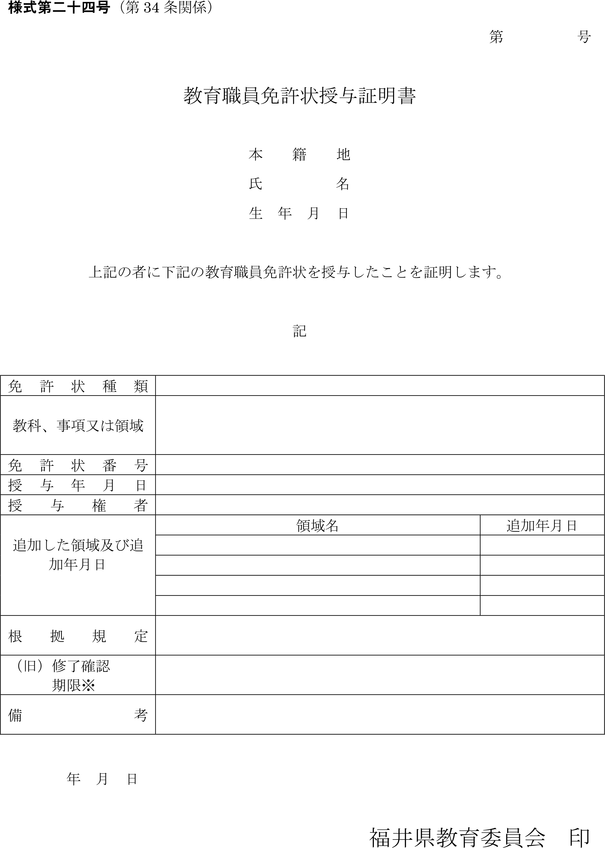○教育職員免許に関する規則
昭和三十年一月二十八日福井県教育委員会規則第三号
教育職員免許に関する規則を次のように制定する。
教育職員免許に関する規則
教育職員免許に関する規則(昭和二十四年福井県教育委員会規則第十号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 教育職員検定(第三条―第六条)
第三章 単位の修得方法(第七条・第七条の二)
第四章 出願の手続(第八条―第十九条)
第五章 審理等(第二十条―第二十一条)
第六章 雑則(第二十三条―第三十六条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 福井県教育委員会(以下「委員会」という。)が授与する教育職員の免許状に関しては、法令に別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成元年教委規則九号〕
(用語の意義)
第二条 この規則において次の用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
一 免許法 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)
二 施行法 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)
三 施行令 教育職員免許法施行令(昭和二十四年政令第三百三十八号)
四 免許法施行規則 教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)
五 施行法施行規則 教育職員免許法施行法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十七号)
六 改正法 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)
七 旧令 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)または旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)
一部改正〔平成二一年教委規則四号・令和四年九号〕
第二章 教育職員検定
(教育職員検定)
第三条 免許法第六条に定める受検者の人物の検定については、面接によることができる。
2 実務の検定に当り技術に関する事項を認定することが困難な場合には、その技術に関する試験を行うことができる。
(特別免許状)
第三条の二 特別免許状を授与する場合の人物の検定は、面接によることができる。
2 免許法第五条第四項の規定による意見の聴取に関し必要な事項は、福井県教育委員会教育長(以下「県教育長」という。)が定める。
追加〔平成元年教委規則九号〕、一部改正〔平成一四年教委規則一〇号・二一年四号・令和四年九号〕
(臨時免許状)
第四条 臨時免許状を授与する場合の学力の検定は、学校の成績証明書または試験によつて行なう。
2 前項の試験については、別に定める。
全部改正〔昭和三五年教委規則二号〕
第五条 施行法第一条および第二条の規定による場合を除き、臨時免許状の授与に関しては、次の各号に定めるところによる。
一 幼稚園、小学校、中学校および特別支援学校の助教諭(中学校において職業実習を担任する者を除く。)の臨時免許状は、高等学校を卒業した者(免許法施行規則第六十六条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有するものと認められた者を含む。以下この条において同じ。)で免許法第六条第一項の規定による教育職員検定(以下「教育職員検定」という。)に合格したものに授与する。
二 高等学校助教諭(実習を担任する者を除く。)の臨時免許状は、次の各号の一に該当する者で教育職員検定に合格したものに授与する。
イ 大学に二年以上在学し、かつ、六十二単位以上を修得した者
ロ 高等専門学校を卒業した者
ハ 旧国立養護教諭養成所を卒業した者
ニ 旧国立工業教員養成所を卒業した者
ホ 高等学校を卒業し、特殊の技能を有する者
ヘ 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中学校、高等女学校または実業学校を卒業し、特殊の技能を有する者
ト 小学校または中学校の教諭の普通免許状を有する者
三 職業実習を担任する中学校助教諭の臨時免許状は、次の各号の一に該当する者で教育職員検定に合格したものに授与する。
イ 高等学校を卒業した者
ロ 改正法附則第二十項に規定する者
四 実習を担任する高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号の一に該当する者で教育職員検定に合格したものに授与する。
イ 第二号に掲げる者
ロ 改正法附則第二十一項に規定する者
五 養護助教諭の臨時免許状は、次の各号の一に該当する者で教育職員検定に合格したものに授与する。
イ 高等学校(旧中等学校令による高等女学校を含む。以下この号ロおよびハにおいて同じ。)を卒業し、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条の規定による看護師の免許を有する者
ロ 高等学校を卒業し、保健師助産師看護師法による准看護師の免許を有する者
ハ 高等学校を卒業し、保健師助産師看護師法第五十三条第一項の規定に該当する者
ニ 免許法附則第七項に規定する者
ホ 保健体育、保健または家庭の教科についての中学校または高等学校の教諭の普通免許状を有する者
全部改正〔昭和三五年教委規則二号〕、一部改正〔昭和三六年教委規則三号・三八年八号・三九年二号・四六年四号・平成元年九号・一四年二号・一〇号・一九年三号〕
(外国で授与された免許状を有する者等)
第六条 免許法第十八条の規定により免許状を授与する場合の学力の検定は、卒業(修了)学校成績証明書または試験によつてこれを行う。
2 前項の試験については、別に定める。
全部改正〔昭和三五年教委規則二号〕
第三章 単位の修得方法
全部改正〔平成一〇年教委規則七号〕
第七条 免許法別表第三、別表第六または別表第六の二の規定による教育職員検定により一種免許状または二種免許状の授与を受けようとする者で、同法別表第三備考第七号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の各号の表の第一欄に掲げる在職年数の区分に応じ、当該各号の第二欄に掲げる科目の単位を含めてそれぞれ同表の第三欄に掲げる単位を修得するものとする。
一 小学校教諭の二種免許状を有する者が小学校教諭の一種免許状を取得する場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
五 | 四 | 二一 | 五 | 四五 |
六 | 三 | 二一 | 四 | 四〇 |
七 | 三 | 一八 | 四 | 三五 |
八 | 三 | 一六 | 四 | 三〇 |
九 | 二 | 一五 | 三 | 二五 |
一〇 | 二 | 一三 | 三 | 二〇 |
一一 | 二 | 一〇 | 三 | 一五 |
一二 | 一 | 七 | 二 | 一〇 |
二 小学校助教諭の臨時免許状を有する者が小学校教諭の二種免許状を取得する場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
六 | 四 | 二九 | 二 | 四五 |
七 | 三 | 二六 | 二 | 四〇 |
八 | 三 | 二三 | 二 | 三五 |
九 | 三 | 二〇 | 二 | 三〇 |
一〇 | 二 | 一八 | 二 | 二五 |
一一 | 二 | 一四 | 二 | 二〇 |
一二 | 二 | 一一 | 二 | 一五 |
一三 | 一 | 八 | 一 | 一〇 |
三 中学校教諭の二種免許状を有する者が中学校教諭の一種免許状を取得する場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
五 | 一〇 | 一六 | 四 | 四五 |
六 | 九 | 一六 | 三 | 四〇 |
七 | 八 | 一四 | 三 | 三五 |
八 | 七 | 一三 | 三 | 三〇 |
九 | 六 | 一一 | 三 | 二五 |
一〇 | 五 | 九 | 三 | 二〇 |
一一 | 四 | 八 | 三 | 一五 |
一二 | 三 | 五 | 二 | 一〇 |
四 中学校助教諭の臨時免許状を有する者が中学校教諭の二種免許状を取得する場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
六 | 一〇 | 二一 | 四 | 四五 |
七 | 九 | 一九 | 三 | 四〇 |
八 | 八 | 一七 | 三 | 三五 |
九 | 七 | 一五 | 三 | 三〇 |
一〇 | 六 | 一四 | 二 | 二五 |
一一 | 五 | 一一 | 二 | 二〇 |
一二 | 四 | 九 | 二 | 一五 |
一三 | 三 | 六 | 一 | 一〇 |
五 高等学校助教諭の臨時免許状を有する者が高等学校教諭の一種免許状を取得する場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
五 | 一〇 | 一二 | 八 | 四五 |
六 | 九 | 一二 | 七 | 四〇 |
七 | 八 | 一一 | 六 | 三五 |
八 | 七 | 一〇 | 六 | 三〇 |
九 | 六 | 九 | 五 | 二五 |
一〇 | 五 | 七 | 五 | 二〇 |
一一 | 四 | 七 | 四 | 一五 |
一二 | 三 | 四 | 三 | 一〇 |
六 幼稚園教諭の二種免許状を有する者が幼稚園教諭の一種免許状を取得する場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 領域に関する専門的事項に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
五 | 四 | 二〇 | 六 | 四五 |
六 | 三 | 二〇 | 五 | 四〇 |
七 | 三 | 一八 | 四 | 三五 |
八 | 三 | 一六 | 四 | 三〇 |
九 | 二 | 一四 | 四 | 二五 |
一〇 | 二 | 一二 | 四 | 二〇 |
一一 | 二 | 一〇 | 三 | 一五 |
一二 | 一 | 七 | 二 | 一〇 |
七 幼稚園助教諭の臨時免許状を有する者が幼稚園教諭の二種免許状を取得する場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 領域に関する専門的事項に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
六 | 五 | 三〇 | | 四五 |
七 | 四 | 二七 | | 四〇 |
八 | 四 | 二四 | | 三五 |
九 | 三 | 二二 | | 三〇 |
一〇 | 三 | 一九 | | 二五 |
一一 | 二 | 一六 | | 二〇 |
一二 | 二 | 一三 | | 一五 |
一三 | 一 | 九 | | 一〇 |
八 免許法施行規則第十一条第一項の表備考第三号の規定の適用を受ける者が小学校教諭の一種免許状を取得する場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
三 | 二 | 一三 | 五 | 二五 |
四 | 二 | 一一 | 四 | 二〇 |
五 | 二 | 一〇 | 三 | 一五 |
六 | 一 | 七 | 二 | 一〇 |
九 免許法施行規則第十一条第一項の表備考第三号の規定の適用を受ける者が中学校教諭の一種免許状を取得する場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
三 | 六 | 一〇 | 四 | 二五 |
四 | 五 | 九 | 三 | 二〇 |
五 | 四 | 八 | 三 | 一五 |
六 | 三 | 五 | 二 | 一〇 |
十 免許法施行規則第十一条第一項の表備考第三号の規定の適用を受ける者が高等学校教諭の一種免許状を取得する場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
三 | 五 | 七 | 八 | 二五 |
四 | 五 | 七 | 五 | 二〇 |
五 | 四 | 七 | 四 | 一五 |
六 | 三 | 四 | 三 | 一〇 |
十一 免許法施行規則第十一条第一項の表備考第三号の規定の適用を受ける者が幼稚園教諭の一種免許状を取得する場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 領域に関する専門的事項に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
三 | 二 | 一二 | 六 | 二五 |
四 | 二 | 一一 | 四 | 二〇 |
五 | 二 | 一〇 | 三 | 一五 |
六 | 一 | 七 | 二 | 一〇 |
十二 改正法附則第八項の規定の適用を受ける者が高等学校教諭(実習を担任する者を除く。)の一種免許状を取得する場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
一〇 | 二〇 | 二四 | 一六 | 九〇 |
一一 | 一九 | 二三 | 一五 | 八五 |
一二 | 一八 | 二一 | 一四 | 八〇 |
一三 | 一七 | 二〇 | 一四 | 七五 |
一四 | 一六 | 一九 | 一三 | 七〇 |
一五 | 一五 | 一八 | 一二 | 六五 |
一六 | 一四 | 一七 | 一一 | 六〇 |
一七 | 一三 | 一五 | 一〇 | 五五 |
一八 | 一二 | 一四 | 一〇 | 五〇 |
一九 | 一〇 | 一三 | 九 | 四五 |
二〇 | 九 | 一一 | 八 | 四〇 |
二一 | 八 | 一〇 | 七 | 三五 |
二二 | 七 | 九 | 六 | 三〇 |
二三 | 六 | 八 | 五 | 二五 |
二四 | 五 | 七 | 五 | 二〇 |
二五 | 四 | 五 | 四 | 一五 |
二六 | 三 | 四 | 三 | 一〇 |
十三 免許法施行規則附則第三十八項の規定の適用を受ける者が保健の教科についての高等学校教諭の一種免許状を取得する場合
イ 修業年限が三年の看護師養成施設を卒業した者
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
四 | 一〇 | 一二 | 八 | 四五 |
五 | 九 | 一一 | 七 | 四〇 |
六 | 八 | 一〇 | 七 | 三五 |
七 | 七 | 九 | 六 | 三〇 |
八 | 六 | 八 | 六 | 二五 |
九 | 五 | 七 | 五 | 二〇 |
一〇 | 四 | 六 | 四 | 一五 |
一一 | 三 | 四 | 三 | 一〇 |
ロ 修業年限が二年の看護師養成施設を卒業した者
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
六 | 一三 | 一六 | 一一 | 六〇 |
七 | 一二 | 一五 | 一〇 | 五五 |
八 | 一一 | 一四 | 九 | 五〇 |
九 | 一〇 | 一二 | 九 | 四五 |
一〇 | 九 | 一一 | 八 | 四〇 |
一一 | 八 | 一〇 | 七 | 三五 |
一二 | 七 | 八 | 七 | 三〇 |
一三 | 六 | 七 | 六 | 二五 |
一四 | 五 | 六 | 五 | 二〇 |
一五 | 四 | 五 | 四 | 一五 |
一六 | 三 | 四 | 三 | 一〇 |
十四 養護教諭の二種免許状を有する者が養護教諭の一種免許状を取得する場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 養護に関する科目 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
三 | 八 | 六 | 二 | 二〇 |
四 | 八 | 五 | 二 | 一五 |
五 | 五 | 四 | 一 | 一〇 |
十五 養護助教諭の臨時免許状を有する者(当分の間、免許法施行規則第六十九条の二に規定する者を含む。)が養護教諭の二種免許状を取得する場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 養護に関する科目 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
六 | 一四 | 八 | 二 | 三〇 |
七 | 一二 | 七 | 二 | 二五 |
八 | 一〇 | 六 | 二 | 二〇 |
九 | 八 | 五 | 二 | 一五 |
一〇 | 五 | 四 | 一 | 一〇 |
十六 栄養教諭の二種免許状を有する者が栄養教諭の一種免許状を取得する場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 管理栄養士学校指定規則別表第一に掲げる教育内容に係る科目 | 栄養に係る教育に関する科目 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 最低修得単位数 |
三 | 三二 | 二 | 六 | 四〇 |
四 | 二七 | 二 | 六 | 三五 |
五 | 二三 | 二 | 五 | 三〇 |
六 | 一八 | 二 | 五 | 二五 |
七 | 一四 | 二 | 四 | 二〇 |
八 | 一〇 | 一 | 四 | 一五 |
九 | 六 | 一 | 三 | 一〇 |
全部改正〔平成一〇年教委規則七号〕、一部改正〔平成一二年教委規則一五号・一四年二号・一七年四号・二一年四号・三一年二号〕
第七条の二 免許法別表第八の規定による教育職員検定により一種免許状または二種免許状の授与を受けようとする者で、免許法施行規則第十八条の二の表備考第四号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の各号の表の第一欄に掲げる在職年数の区分に応じ、当該各号の第二欄に掲げる科目の単位を含めてそれぞれ同表の第三欄に掲げる単位を修得するものとする。
一 幼稚園教諭の普通免許状を有する者が小学校教諭の二種免許状を取得する場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
道徳の理論及び指導法 | 生徒指導の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法、進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 |
一 | | 七 | 一 | 二 | | 一〇 |
二 | | 五 | 一 | 一 | | 七 |
二 中学校教諭の普通免許状を有する者が小学校教諭の二種免許状を取得する場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
道徳の理論及び指導法 | 生徒指導の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法、進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 |
一 | | 七 | | 二 | | 九 |
二 | | 五 | | 一 | | 六 |
三 小学校教諭の普通免許状を有する者が中学校教諭の二種免許状を取得する場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
道徳の理論及び指導法 | 生徒指導の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法、進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 |
一 | 七 | 二 | | 二 | | 一一 |
二 | 五 | 一 | | 二 | | 八 |
三 | 五 | 一 | | 一 | | 七 |
四 高等学校教諭の普通免許状を有する者が中学校教諭の二種免許状を取得する場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
道徳の理論及び指導法 | 生徒指導の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法、進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 |
一 | | 一 | 一 | 一 | 三 | 六 |
二 | | 一 | 一 | 一 | 二 | 五 |
五 中学校教諭の普通免許状(二種免許状を除く。)を有する者が高等学校教諭の一種免許状を取得する場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
道徳の理論及び指導法 | 生徒指導の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法、進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 |
一 | | 一 | | 二 | 六 | 九 |
二 | | 一 | | 一 | 四 | 六 |
六 小学校教諭の普通免許状を有する者が幼稚園教諭の二種免許状を取得する場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
道徳の理論及び指導法 | 生徒指導の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法、進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 |
一 | | 三 | | | | 三 |
追加〔平成三〇年教委規則三号〕、一部改正〔平成三一年教委規則二号〕
第七条の三 前二条に定めるもののほか、免許法別表第三、別表第六、別表第六の二または別表第八の規定による教育職員検定により一種免許状または二種免許状の授与を受けようとする者で、同法別表第三備考第七号の規定または免許法施行規則第十八条の二の表備考第四号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法については、県教育長が定める。
全部改正〔平成一〇年教委規則七号〕、一部改正〔平成一七年教委規則四号・二一年四号・三〇年三号〕
第四章 出願の手続
(免許状授与)
第八条 免許法第五条第一項の規定による免許状の授与を願い出る者は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
一 教育職員免許状授与願(
様式第一号。以下同じ。)
三 免許法第五条第一項に規定する基礎資格の証明書
四 学力に関する証明書(単位修得証明書を含む。以下同じ。)
五 宣誓書(
様式第三号。ただし、現に福井県において教育職員の身分を有する者は、これを省くことができる。以下同じ。)
六 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成九年文部省令第四十号)第四条第一項に定める介護等の体験に関する証明書
一部改正〔昭和三一年教委規則七号・三六年三号・平成元年九号・一〇年七号・一二年一五号・二一年四号〕
第八条の二 免許法第十六条第一項または第十六条の四第一項の規定による免許状の授与を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
一 教育職員免許状授与願
二 履歴書
三 免許法第十六条第一項または第十六条の四第三項に規定する教員資格認定試験の合格証明書
四 宣誓書
追加〔昭和三九年教委規則六号〕、一部改正〔平成元年教委規則九号・一二年一五号・令和四年九号〕
第八条の三 免許法附則第八項の規定による免許状の授与を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
一 教育職員免許状授与願
二 履歴書
三 国立工業教員養成所の卒業証明書
四 宣誓書
追加〔平成一二年教委規則一七号〕、一部改正〔平成一四年教委規則一〇号〕
第八条の四 教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百二十二号)附則第六項の規定による免許状の授与を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
一 教育職員免許状授与願
二 履歴書
三 図画工作または職業の教科の中学校教諭免許状の写し
四 技術の教科に関する講習の修了証書の写し
五 宣誓書
追加〔平成一二年教委規則一七号〕
第八条の五 教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十九号)附則第二項の規定による免許状の授与を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
一 教育職員免許状授与願
二 履歴書
三 数学、理科、看護、家庭、農業、工業、商業、水産、情報技術または情報処理の教科の高等学校教諭の普通免許状の写し
四 情報の教科に関する講習の修了証書の写し
五 宣誓書
追加〔平成一二年教委規則一七号〕
第八条の六 教育職員免許法等の一部を改正する法律附則第三項の規定による免許状の授与を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
一 教育職員免許状授与願
二 履歴書
三 公民、家庭または看護の教科の高等学校教諭の普通免許状の写し
四 福祉の教科に関する講習の修了証書の写し
五 宣誓書
追加〔平成一二年教委規則一七号〕、一部改正〔平成三〇年教委規則三号〕
(教育職員検定)
第九条 教育職員検定(特別免許状に係るものを除く。)を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
二 履歴書
三 基礎資格となる次の証明書のうち必要なもの
イ 基礎資格となる学校の卒業または修了証明書
ロ 教育職員免許状の写
ハ 前各号のほか資格を証明するもの
四 学力に関する証明書等のうち必要なもの
イ 卒業または修了成績証明書
ロ 学力に関する証明書
ハ 前各号のほか学力を証明するもの
七 教科に関する証明書(
様式第七号。必要があるものに限る。以下同じ。)
九 宣誓書
十 普通免許状所有者を採用することができない旨の所轄庁の事由書(
様式第九号。臨時免許状の場合に限る。第十四条第十号の場合においても同様とする。)
2 臨時免許状の教育職員検定を願い出る場合には、前項第五号の書類は必要としない。
一部改正〔昭和三一年教委規則七号・三六年三号・平成元年九号・一二年一五号・二一年四号・三〇年三号〕
第十条 特別免許状に係る教育職員検定を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
一 教育職員検定願
二 履歴書
三 人物に関する証明書
四 身体に関する証明書
五 担当する教科に関する専門的な知識経験または技能を有する者であることを証する書類
六 宣誓書
追加〔平成元年教委規則九号〕、一部改正〔平成一二年教委規則一五号・一三年一号・一四年一〇号〕
第十一条 外国において授与された教育職員に関する免許状を有する者または外国の学校を卒業し、もしくは修了した者で、免許法第十八条の規定による教育職員検定を願い出るものは、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
一 教育職員検定願
二 履歴書
三 学校の卒業または修了証明書および成績証明書またはこれに代るもの
四 免許状の写し(必要があるものに限る。)
五 人物に関する証明書
六 実務に関する証明書(必要があるものに限る。)
七 学力に関する証明書(必要があるものに限る。)
八 身体に関する証明書
九 宣誓書
一部改正〔平成元年教委規則九号・一二年一五号・二一年四号〕
(自立教科等の免許状の授与および教育職員検定)
第十二条 免許法施行規則第六十四条の規定による自立教科等の免許状の授与または教育職員検定を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
一 自立教科等教育職員免許状授与(検定)願(
様式第十一号または第十二号)
二 履歴書
三 基礎資格に関する証明書のうち必要なもの
イ 教育養成機関の卒業または修了証明書
ロ 教育職員免許状の写し
ハ あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許に関する証書の写し
四 学力に関する証明書(検定を受ける場合に限る。)
五 実務に関する証明書(検定を受ける場合に限る。)
六 人物に関する証明書(検定を受ける場合に限る。)
七 身体に関する証明書(検定を受ける場合に限る。)
八 宣誓書
一部改正〔昭和三一年教委規則七号・四〇年四号・平成元年九号・一二年一五号・一九年三号・二一年四号〕
(旧令による教員免許状を有する者の免許状交付)
第十三条 旧令による教員免許状を有する者で、施行法第一条第三項の規定により、教育職員免許状の交付を願い出るものは、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
二 履歴書
三 旧令による教員免許状の写しまたはその授与証明書
四 教科に関する証明書(必要があるものに限る。)
五 宣誓書
一部改正〔昭和三一年教委規則七号・平成元年九号・一二年一五号〕
(従前の規定による学校の卒業者等に対する教育職員検定)
第十四条 施行法第二条の規定により教育職員検定を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
一 教育職員検定願
二 履歴書
三 基礎資格に関する次の証明書のうち必要なもの
イ 学校の卒業または修了証明書および成績証明書
ロ 旧令による教員免許状の写しまたは学士または学位の称号証明書
ハ 教育職員免許状の写し
ニ 無線通信士、無線技術士、航海士または機関士資格証明書の写し
ホ 前各号のほか、委員会が必要と認める証明書
四 教科に関する証明書(必要があるものに限る。)
五 削除
六 実務に関する証明書(必要があるものに限る。)
七 人物に関する証明書
八 身体に関する証明書
九 宣誓書
十 普通免許状所有者を採用することができない旨の所轄庁の事由書
一部改正〔昭和三一年教委規則七号・三六年三号・平成元年九号・一二年一五号〕
(所要資格証明書)
第十五条 免許法施行規則附則第十七項の規定により所要資格を得た旨の証明書の交付を願い出る者は、その受けようとする資格ごとに次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
二 履歴書
三 基礎資格に関する次の証明書のうち必要なもの
イ 教育職員免許状の写し
ロ 学校の卒業または修了証明書
ハ 保健師または看護師の免許に関する証書の写し
四 実務に関する証明書(必要があるものに限る。)
五 学力に関する証明書(必要があるものに限る。)
一部改正〔昭和三六年教委規則三号・平成元年九号・一四年二号・二一年四号・三〇年三号〕
(書換または再交付)
第十六条 免許状の書換または再交付を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
一 教育職員免許状書換(再交付)願(
様式第十五号または第十六号)
二 教育職員免許状(書換の場合に限る。)または免許状下付証明書(再交付の場合に限る。)
三 戸籍抄本(必要があるものに限る。)
四 書換または再交付を必要とする理由書(必要があるものに限る。)
五 紛失、焼失、盗難等による場合は、相当官公署の作成した事実証明書
一部改正〔昭和三六年教委規則三号・平成元年九号〕
(免許状の授与証明)
第十七条 委員会が授与した免許状に係る授与証明書の交付を受けようとする者は、教育職員免許状授与証明書交付願(
様式第十七号の二)を委員会に提出するものとする。
追加〔令和四年教委規則九号〕
(願書)
第十八条 免許状の授与、書換、再交付または教育職員検定を願い出る場合は、免許状の種類ごとにその書類を提出しなければならない。
一部改正〔昭和三九年教委規則三二号・平成元年九号・一二年七号・令和四年九号〕
(出願書類の経由等)
第十九条 現に教育職員として在職している者が、第九条から第十六条までの書類を提出する場合には、学校長(園長を含む。)を経由しなければならない。
一部改正〔令和四年教委規則九号〕
第二十条 第八条から第十五条までに掲げる書類のうち、人物に関する証明書、実務に関する証明書、出身学校の成績証明書および教科に関する証明書は、親展文書とし、出願書類の末尾に添付しなければならない。
一部改正〔令和四年教委規則九号〕
第五章 審理等
(免許状の返納)
第二十一条 免許法第十条第二項(同法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定による免許状の返納は、免許状返納書(
様式第十七号の三)を添えてしなければならない。
全部改正〔平成一四年教委規則一〇号〕、一部改正〔平成二一年教委規則四号・令和四年九号〕
(免許状の取上げ)
第二十二条 免許法第十一条第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 処分を受けた者の氏名および現住所
二 取り上げる免許状の種類(教科名、番号および授与権者名)
全部改正〔平成一四年教委規則一〇号〕、一部改正〔平成二一年教委規則四号・令和四年九号〕
第六章 雑則
一部改正〔平成二一年教委規則四号・令和四年九号〕
(非常勤講師の任命等の届出)
第二十三条 免許法第三条の二第二項の規定により、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を非常勤の講師として任命し、または雇用しようとする者は、非常勤講師による教授(実習)届出書(
様式第十八号)を委員会に提出しなければならない。
追加〔平成元年教委規則九号〕、一部改正〔平成一〇年教委規則七号・令和四年九号〕
(施行法第一条および第二条の免許状の教科)
第二十四条 施行法施行規則第一条に規定する旧令による教員免許状に記載した科目に相当する新免許状の教科は、次の表の定めるところによる。
旧令による教員免許状に記載された学科目 | 有するものとみなされた教員免許状の教科 |
中学校高等女学校の教員免許状の場合 | 中学校の教員免許状の場合 | 高等学校の教員免許状の場合 |
国民科 修身 | 社会 | 社会 |
同 国語 | 国語 | 国語 |
同 歴史 | 社会 | 社会 |
同 地理 | 社会 | 社会 |
理数科 数学 | 数学 | 数学 |
同 物象 | 理科 | 理科 |
同 生物 | 理科 | 理科 |
家政科 家政 | 家庭 | 家庭 |
同 育児 | 家庭 | 家庭 |
同 保健 | 家庭または保健 | 家庭または保健 |
同 被服 | 家庭 | 家庭 |
体錬科 体操 | 保健体育 | 保健体育 |
芸能科 音楽 | 音楽 | 音楽 |
同 書道 | 国語 | 書道 |
同 図画 | 美術 | 美術 |
同 工作 | 美術 | 工芸 |
実業科のうち 農業 | 職業 | 農業 |
同 工業 | 職業 | 工業 |
同 商業 | 職業 | 商業 |
同 水産 | 職業 | 水産 |
外国語科のうち英語 | 外国語(英語) | 外国語(英語) |
同 独語 | 外国語(ドイツ語) | 外国語(ドイツ語) |
同 仏語 | 外国語(フランス語) | 外国語(フランス語) |
同 支那語 | 外国語(中国語) | 外国語(中国語) |
同 マライ語 | 外国語(マライ語) | 外国語(マライ語) |
旧令による教員免許状に記載された学科目 | 有するものとみなされた教員免許状の教科 |
実業学校の教員免許状の場合 | 中学校の教員免許状の場合 | 高等学校の教員免許状の場合 |
機械 | 職業 | 工業 |
採鉱 | 職業 | 工業 |
紡織 | 職業 | 工業 |
木材工芸 | 職業 | 工業 |
電気 | 職業 | 工業 |
や金 | 職業 | 工業 |
色染 | 職業 | 工業 |
金属工芸 | 職業 | 工業 |
土木 | 職業 | 工業 |
応用化学 | 職業 | 工業 |
図案 | 美術 | 美術 |
建築 | 職業 | 工業 |
窯業 | 職業 | 工業 |
印刷工芸 | 職業 | 工業 |
耕種 | 職業 | 農業 |
農業経済 | 職業 | 農業 |
蚕業 | 職業 | 農業 |
林業 | 職業 | 農業 |
畜産 | 職業 | 農業 |
獣医 | 職業 | 農業 |
農芸化学 | 職業 | 農業 |
商事要項 | 職業 | 商業 |
商業英語 | 外国語(英語) | 外国語(英語) |
簿記 | 職業 | 商業 |
支那語 | 外国語(中国語) | 外国語(中国語) |
商業算術 | 職業または数学 | 商業または数学 |
商品 | 職業 | 商業 |
漁ろう | 職業 | 水産 |
製造 | 職業 | 水産 |
養殖 | 職業 | 水産 |
たん工実習 | 職業実習 | 工業実習 |
電気工作実習 | 職業実習 | 工業実習 |
塗工実習 | 職業実習 | 工業実習 |
分析実習 | 職業実習 | 工業実習 |
色染実習 | 職業実習 | 工業実習 |
家具実習 | 職業実習 | 工業実習 |
たん金実習 | 職業実習 | 工業実習 |
鋳工実習 | 職業実習 | 工業実習 |
電気取扱実習 | 職業実習 | 工業実習 |
測量実習 | 職業実習 | 工業実習 |
窯業実習 | 職業実習 | 工業実習 |
紡績実習 | 職業実習 | 工業実習 |
ひき物実習 | 職業実習 | 工業実習 |
きゆう漆実習 | 職業実習 | 工業実習 |
機械製図実習 | 職業実習 | 工業実習 |
採鉱実習 | 職業実習 | 工業実習 |
木型実習 | 職業実習 | 工業実習 |
建築製図実習 | 職業実習 | 工業実習 |
と金実習 | 職業実習 | 工業実習 |
製版実習 | 職業実習 | 工業実習 |
彫金実習 | 職業実習 | 工業実習 |
描金実習 | 職業実習 | 工業実習 |
機械仕上実習 | 職業実習 | 工業実習 |
造船実習 | 職業実習 | 工業実習 |
大工実習 | 職業実習 | 工業実習 |
や金実習 | 職業実習 | 工業実習 |
織物実習 | 職業実習 | 工業実習 |
印刷実習 | 職業実習 | 工業実習 |
鋳金実習 | 職業実習 | 工業実習 |
木地実習 | 職業実習 | 工業実習 |
彫そ実習 | 職業実習 | 工業実習 |
蚕業実習 | 職業実習 | 農業実習 |
林業実習 | 職業実習 | 農業実習 |
てい鉄実習 | 職業実習 | 農業実習 |
農場実習 | 職業実習 | 農業実習 |
珠算 | 職業実習 | 商業実習 |
商業実践 | 職業実習 | 商業実習 |
タイプライチング | 職業実習 | 商業実習 |
漁ろう実習 | 職業実習 | 水産実習 |
製造実習 | 職業実習 | 水産実習 |
養殖実習 | 職業実習 | 水産実習 |
旧令による教員免許状に記載された学科目 | 有するものとみなされた教員免許状の教科 |
高等学校高等科教員免許状の場合 | 中学校の教員免許状の場合 | 高等学校の教員免許状の場合 |
修身 | 社会 | 社会 |
国語 | 国語 | 国語 |
漢文 | 国語 | 国語 |
英語 | 外国語(英語) | 外国語(英語) |
仏語 | 外国語(フランス語) | 外国語(フランス語) |
独語 | 外国語(ドイツ語) | 外国語(ドイツ語) |
日本史および東洋史 | 社会 | 社会 |
西洋史 | 社会 | 社会 |
地理 | 社会 | 社会 |
哲学概況 | 社会 | 社会 |
心理および論理 | 社会 | 社会 |
法制および経済 | 社会 | 社会 |
数学 | 数学 | 数学 |
物理 | 理科 | 理科 |
化学 | 理科 | 理科 |
植物 | 理科 | 理科 |
動物 | 理科 | 理科 |
地質および鉱物 | 理科 | 理科 |
図画 | 美術 | 美術 |
旧令による教員免許状に記載された学科目 | 有するものとみなされた教員免許状の教科 |
高等女学校高等科および専攻科の教員免許状の場合 | 中学校の教員免許状の場合 | 高等学校の教員免許状の場合 |
家政科 家庭 | 家庭 | 家庭 |
同 育児 | 家庭 | 家庭 |
同 保健 | 家庭または保健 | 家庭または保健 |
同 被服 | 家庭 | 家庭 |
旧令による教員免許状に記載された学科目 | 有するものとみなされた教員免許状の教科 |
国民学校専科教員免許状の場合 | 中学校の教員免許状の場合 |
音楽 | 音楽 |
体操 | 保健体育 |
裁縫 | 家庭 |
家事 | 家庭または保健 |
工作 | 美術 |
図画 | 美術 |
農業 | 職業 |
工業 | 職業 |
商業 | 職業 |
水産 | 職業 |
一部改正〔昭和三一年教委規則七号・三六年三号・三八年八号・平成元年九号・令和四年九号〕
第二十五条 施行法第二条第一項の表の下欄に掲げる中学校または高等学校の教員の免許状の教科については、施行法施行規則第二条第一項の規定に従い、次の表の定めるところによる。
施行法第二条第一項の表の上欄に掲げるもの | 中学校教員免許状の場合 | 高等学校教員免許状の場合 |
第一号 | 成績良好な旨の出身学校長または実務証明責任者の証明のある教科 | |
第二号 | 同右 | その学校において修めた学科目に相当する実業に関する教科 |
第三号 | 同右 | 同右 |
第四号 | その専攻した学科目に相当する教科または、それに類する教科でその教科について成績良好な旨の出身学校長または実務証明責任者の証明のある教科 | 同上 |
第五号 | 同右 | 同右 |
第六号 | 同右 | 同右 |
第七号 | 同右 | 同右 |
第七号の二 | 国民学校専科教員免許状に記載された科目に相当する教科で成績良好な旨の出身学校長または実務証明責任者の証明のある教科 | |
第七号の三 | 同右 | |
第九号 | 教授を担当した教科について成績良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科 | |
第十号 | 同右 | 同上 |
第十二号 | 第四号に同じ | 同上 |
第十三号 | 学位請求論文に関係のある教科または教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科 | 同上 |
第十四号 | 第四号に同じ | 同上 |
第十五号 | 指定または許可の科目に相当する教科およびその関係教科で成績良好な旨の出身学校長または実務証明責任者の証明のある教科 | 同上 |
第十五号の二 | 第四号に同じ | 同上 |
第十六号 | 第九号に同じ | |
第十七号 | 第一号に同じ | |
第十八号 | 教育成績の良好な旨の実務証明責任者の証明のある実習教科 | 同上 |
第十九号 | | 教授を担当した教科について成績良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科 |
第二十号 | 職業 | 工業 |
第二十号の二 | 職業 | 工業 |
第二十号の三 | 職業 | 商船 |
第二十号の四 | 職業 | 商船 |
第二十号の五 | 職業 | 商船 |
第二十五号 | 第一号に同じ | |
一部改正〔昭和三八年教委規則八号・六二年一号・平成元年九号・令和四年九号〕
(教科についての出身学校長の証明)
第二十六条 施行法施行規則第一条および第二条の表に規定する出身学校長の証明は、学業成績証明書とする。
一部改正〔昭和三八年教委規則八号・平成元年九号・令和四年九号〕
(各種証明書の証明書)
第二十七条 第八条から第十六条までの各号に掲げる書類中所轄庁の証明を必要とするものについては、次に定めるところによる。
一 人物、実務および教科に関する証明を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ下欄に掲げる者の作成した証明書とする。
学校の卒業または修了をもつて出願の要件とするもの | 出身学校長 |
教育または実地に関する経験をもつて出願の要件とするもの | 在職した学校または所属長 |
公立の学校または教育施設の長および指導主事 | 所属する教育委員会の教育長 |
開業資格を出願の要件とするもの | 資格を授与した者 |
二 特別の事由により前号の証明書を提出することができない者については、委員会において調査の上、人物、実務および教科に関する証明書を発行することがある。
2 身体に関する証明書は、国立または公立もしくはこれに準ずる医療機関の作成したものでなければならない。
一部改正〔昭和三八年教委規則八号・平成元年九号・令和四年九号〕
(原簿)
第二十八条 免許状の原簿は、免許法施行規則第七十四条第二項に定められた事項を記載し、免許状の種類別に作成するものとする。
全部改正〔平成二一年教委規則四号〕、一部改正〔平成三〇年教委規則三号・令和四年九号〕
第二十九条 所要資格証明書の原簿は、学校の種類別に作成し、その様式は、
様式第二十号による。
一部改正〔昭和三八年教委規則八号・平成元年九号・令和四年九号〕
(書類の保存年限)
第三十条 次に掲げる免許法施行規則第七十六条第一項に規定する書類および免許状等に関する書類の保存年限は、二十年とする。ただし、書類の保存年限が到来した場合であつても、引き続き当該書類を保存する必要があるときは、必要な期間に限り、当該書類の保存年限を延長することができる。
一 教育職員免許状原簿
二 免許法認定講習における単位修得原簿
三 免許状の失効、取上げおよび審査に関する書類
全部改正〔平成一二年教委規則一五号〕、一部改正〔令和四年教委規則九号〕
(特別免許状の様式)
追加〔平成元年教委規則九号〕、一部改正〔令和四年教委規則九号〕
(臨時免許状の様式)
一部改正〔昭和三八年教委規則八号・平成元年九号・令和四年九号〕
(所要資格証明書の様式)
一部改正〔昭和三五年教委規則二号・三八年八号・平成元年九号・令和四年九号〕
(教育職員免許状授与証明書の様式)
追加〔令和四年教委規則九号〕
(公告)
第三十五条 免許状が失効したときまたは免許状取上げの処分を行ったときは、免許法第十三条第一項に規定する手続をとるとともに、免許状の種類、教科、その者の氏名および本籍地を県報により公告するものとする。
一部改正〔昭和三八年教委規則八号・五九年一号・平成一四年一〇号・令和四年九号〕
(委任)
第三十六条 この規則に定めるもののほか、委員会が授与する教育職員の免許状に関し必要な事項は、県教育長が定める。
追加〔平成元年教委規則九号〕、一部改正〔平成二一年教委規則四号・令和四年九号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年十二月三日から適用する。
一部改正〔平成一二年教委規則一七号〕
附 則(昭和三一年教委規則第七号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年教委規則第二号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第一号から第十一号までおよび様式第十三号から第十八号までの改正規定は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和三六年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十条のうち、中学校の教員免許状の場合の改正規定、附則第二項および附則第三項の規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和三八年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和三九年教委規則第三二号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和三九年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和五九年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年教委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十五年三月三十一日までにこの規則による改正前の教育職員免許に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第七条の規定による単位の修得方法により免許法別表第三または別表第六に規定するそれぞれの普通免許状に係る単位数のうち十単位以上を修得した者に対する免許法別表第三または別表第六の規定の適用については、この規則による改正後の教育職員免許に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一部改正〔平成一二年教委規則一五号〕
3 この規則の施行の際現に改正前の規則第三十二条の規定による許可を受けている者は、この規則の施行の日に改正後の規則第三十二条の規定による届出をしたものとみなす。
附 則(平成一二年教委規則第七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年教委規則第一五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成十五年三月三十一日までに第一条の規定による改正前の教育職員免許に関する規則第七条第十二号および第十三号の規定による単位の修得方法により免許法別表第三または別表第六に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、この規則による改正後の教育職員免許に関する規則第七条第十二号および第十三号の規定による単位の修得方法により免許法別表第三または別表第六に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
附 則(平成一二年教委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年教委規則第一号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一四年教委規則第二号)
この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
附 則(平成一四年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十条、第二十一条、第四十三条、様式第三号および様式第十七号の二の改正規定は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年教委規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年教委規則第四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年教委規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年教委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の教育職員免許に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二九年教委規則第二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日教委規則第三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二九日教委規則第二号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日教委規則第一号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和元年一〇月二九日教委規則第四号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日教委規則第三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の教育職員免許に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年一〇月七日教委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の教育職員免許に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
 様式第一号
様式第一号(第8条関係)
全部改正〔平成12年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号・4年1号〕
 様式第二号
様式第二号(第8条関係)
全部改正〔平成12年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕
 様式第3号
様式第3号(第8条関係)
全部改正〔令和元年教委規則4号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕
 様式第四号
様式第四号(第9条関係)
全部改正〔平成12年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号・4年1号〕
 様式第五号
様式第五号全部改正〔昭和35年教委規則2号〕、一部改正〔平成元年教委規則9号〕
 様式第六号
様式第六号(第9条関係)
全部改正〔平成10年教委規則7号〕
 様式第七号
様式第七号全部改正〔昭和35年教委規則2号〕、一部改正〔平成元年教委規則9号〕
 様式第八号
様式第八号(第9条関係)
全部改正〔令和4年教委規則9号〕
 様式第九号
様式第九号(第9条関係)
追加〔平成元年教委規則9号〕
 様式第十号
様式第十号(第10条関係)
追加〔平成元年教委規則9号〕
 様式第十一号
様式第十一号(第12条関係)
全部改正〔平成12年教委規則7号〕、一部改正〔平成19年教委規則3号・令和3年2号・4年1号〕
 様式第十二号
様式第十二号(第12条関係)
全部改正〔平成12年教委規則7号〕、一部改正〔平成19年教委規則3号・令和3年2号・4年1号〕
 様式第十三号
様式第十三号(第13条関係)
全部改正〔平成12年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号・4年1号〕
 様式第十四号
様式第十四号(第15条関係)
全部改正〔平成12年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号・4年1号〕
 様式第十五号
様式第十五号(第16条関係)
全部改正〔平成12年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号・4年1号〕
 様式第十六号
様式第十六号(第16条関係)
全部改正〔平成12年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号・4年1号〕
 様式第十七号
様式第十七号(第16条関係)
全部改正〔平成12年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕
 様式第十七号の二
様式第十七号の二(第17条関係)
追加〔令和4年教委規則9号〕
 様式第十七号の三
様式第十七号の三(第21条関係)
追加〔平成14年教委規則10号〕、一部改正〔平成21年教委規則4号・令和4年9号〕
 様式第十八号
様式第十八号(第23条関係)
全部改正〔平成23年教委規則9号〕、一部改正〔令和4年教委規則9号〕
様式第19号 削除
削除〔平成21年教委規則4号〕
 様式第二十号
様式第二十号全部改正〔昭和35年教委規則2号〕、一部改正〔平成元年教委規則9号〕
 様式第21号
様式第21号(第31条関係)
全部改正〔平成21年教委規則4号〕、一部改正〔令和4年教委規則9号〕
 様式第22号
様式第22号(第32条関係)
全部改正〔平成21年教委規則4号〕、一部改正〔令和4年教委規則9号〕
 様式第二十三号
様式第二十三号一部改正〔平成元年教委規則九号〕
 様式第二十四号
様式第二十四号(第34条関係)
全部改正〔令和4年教委規則9号〕